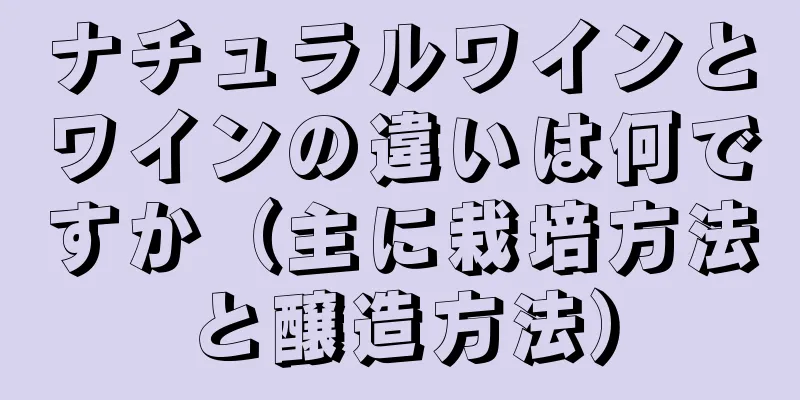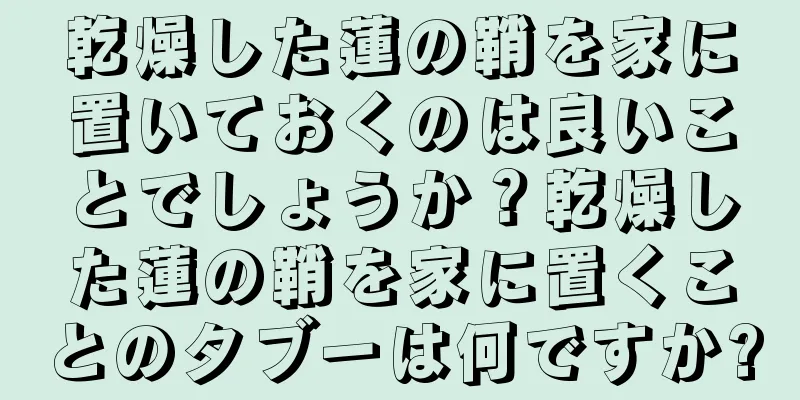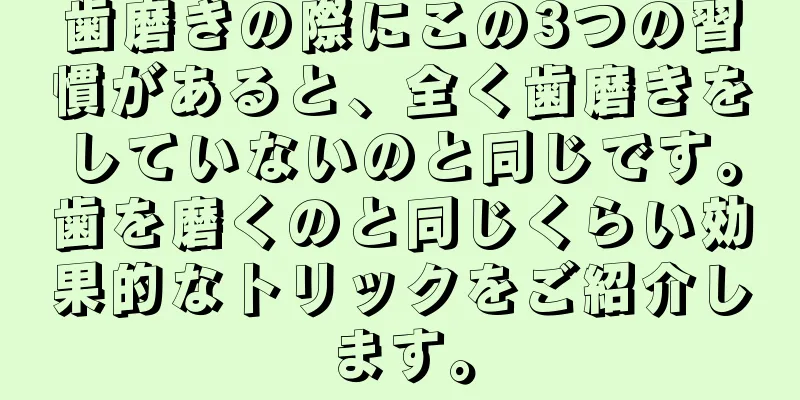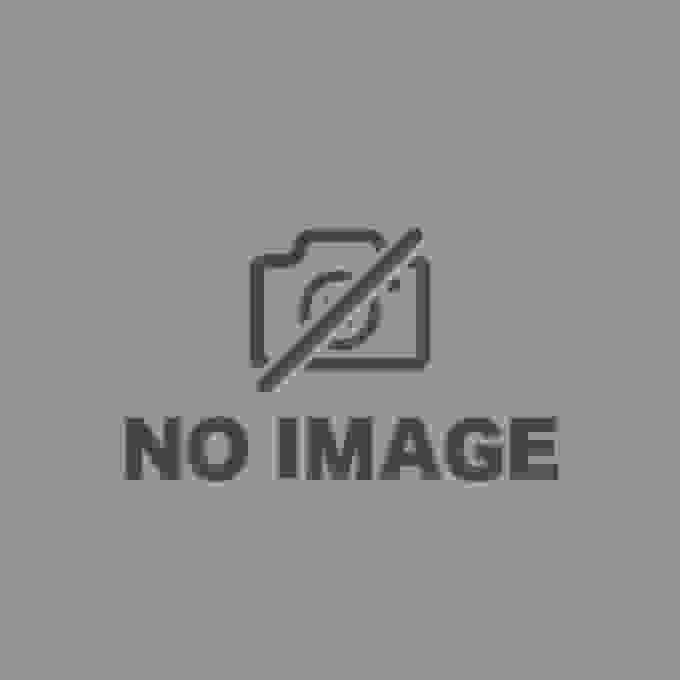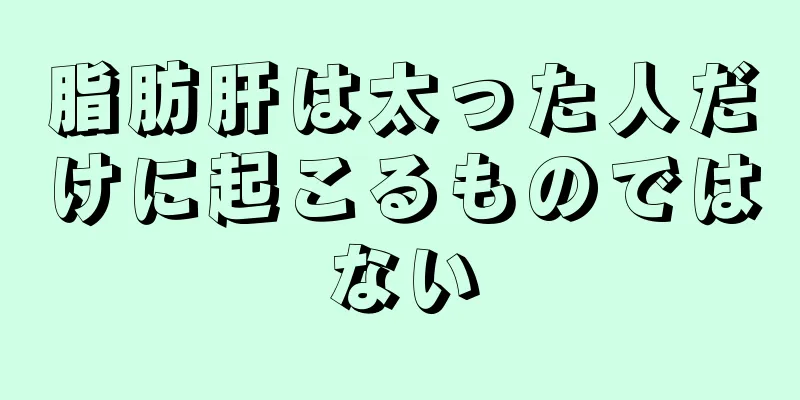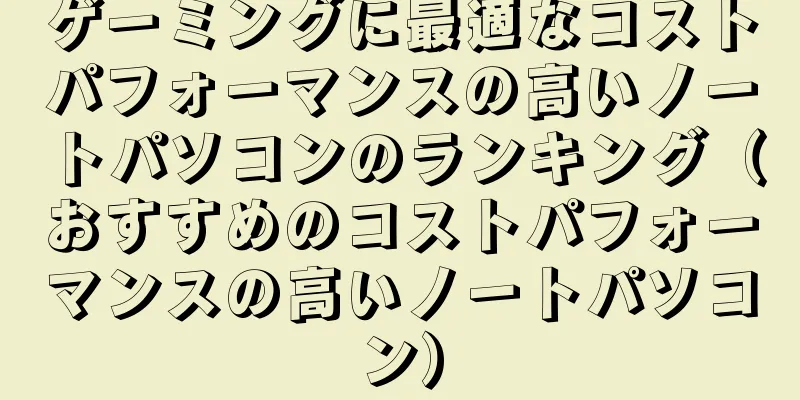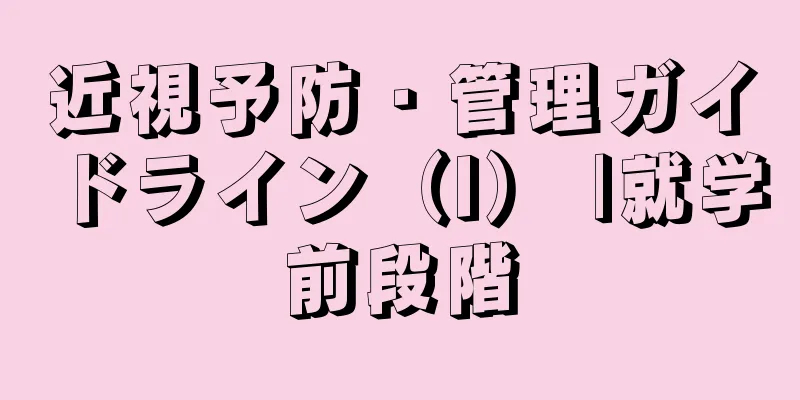強く勧める:目覚めた後しばらくベッドにいることは健康にとても良い
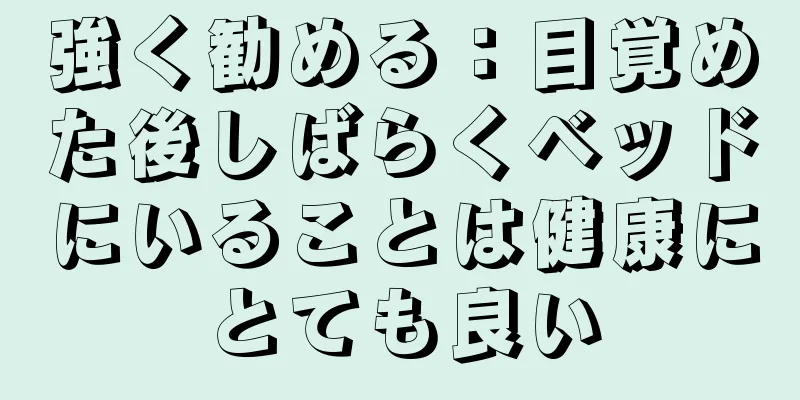
|
アラームが鳴ったら何が起こりますか?私は目覚ましを止めて、急いで起き上がり、眠い目をこすって、トイレに走りました... しかし、これは人間の本性に反するのではないでしょうか?目を開けたら何度も頭痛に見舞われるだろうと思い、目を閉じてもう少し寝ることにしました。天気はどんどん寒くなってきており、起き上がる勇気がありません。私が怠け者なわけではありません。最新の科学的研究でもそう言われています。 朝起きてから30分間ベッドにいることは健康に良い 2023年10月17日、スウェーデンのストックホルム大学の研究者らは、「Issnoozinglosing? 断続的な朝のアラームが使用される理由と、それが睡眠、認知、コルチゾール、気分に及ぼす影響」と題する論文を睡眠研究ジャーナルに発表し、次のように述べています。 朝目覚ましが鳴ってすぐに起きる場合と比べて、繰り返し目覚ましを設定し、最初の目覚ましが鳴った後に 30 分間昼寝をすると、脳の認知能力が向上し、一日を通して身体疲労や感情状態が軽減される可能性があります。 [1] 画像ソース: unsplash.com この研究は2つの部分に分かれています。最初の部分では、研究者らはアンケートの形で、平均年齢34歳(うち66%が女性)の1,732人の参加者から睡眠データを収集した。その結果、69%の人が目覚まし時計の繰り返し機能を使用したり、複数のアラームを設定したりすることが分かりました。各アラーム間の平均間隔は 8 分でした。目覚ましが鳴った後、彼らは平均22分間ベッドに留まりました。 また、この研究では、若者はベッドで寝ていることを好むのに対し、高齢者は目覚ましが鳴るとすぐに起き上がることができることも判明した。 2 つのグループを比較すると、ベッドで過ごすことを好むグループの平均年齢は 6 歳若く、また、彼らは遅くまで寝る傾向があり、遅くまで寝る人の割合はベッドから出ない人よりも 4 倍も高くなります。ベッドで寝ている人は平日の昼寝の時間がやや短く、ベッドで寝ていない人よりも平均13分短い。しかし、2つのグループ間で睡眠の質に違いはありませんでした。 画像ソース: unsplash.com 研究の第2部では、慎重に設計された実験がいくつか含まれており、被験者もベッドで過ごすことを好む31人に絞り込まれました。研究者らは、被験者(心理学実験や心理テストで実験やテストを受けている被験者)の睡眠の質、認知能力、コルチゾールレベル、感情状態を測定した。 結果によると、ベッドで過ごすことを好む被験者は、起床後40分以内の認知能力テストでより良い成績を収め、身体的な疲労と眠気が改善されたという。覚醒時間が長くなるにつれて気分も大幅に改善し、目覚めたばかりのときと比べて、目覚めてから 40 分後にはより社交的になり、より楽観的になった。 そのため研究者たちは、目覚ましが鳴った後30分間ベッドに留まっていても悪影響はないと考えています。むしろ、朝眠い人が完全に目覚め、目覚めた後の認知能力、身体状態、感情状態を改善するのに役立ちます。 画像ソース: unsplash.com 朝、目覚ましが鳴った後、少し長くベッドにいることは、深い眠りやレム睡眠から突然目覚めるのではなく、徐々に目覚めることができるので、健康に良いです。ゆっくりと目覚めることは、脳と体にとってより有益です。 これは、人体が睡眠状態にあるとき、心拍が遅くなり、血液循環が遅くなり、体温が下がり、代謝が遅くなるためです。目覚めた後、人間の体は睡眠中の抑制された状態から興奮した状態に切り替えるプロセスを必要とします。 目覚めたばかりの時は、注意力や認知能力が低下し、知覚や運動能力も低下し、感情調節能力も目覚めていないため、多くの人が「目覚めたときに不機嫌」を感じます。また、目覚ましが鳴った直後にベッドから飛び起きると、体が適応するのに間に合わず、めまい、動悸、起立性低血圧などの症状が出やすくなります。高血圧患者の場合、突然の心血管疾患を引き起こす可能性もあります。 しばらくベッドで過ごすことで、心臓血管系が徐々に適応する機会が与えられ、また、体全体の筋肉や関節を目覚めさせる合図としても機能します。起きた後は、しばらくベッドに座り、手足や首、関節を動かして体を活動状態にしてみるのもよいでしょう。反応が正常であると感じたら、ゆっくりとベッドから起き上がってください。 画像ソース: unsplash.com 冬が近づいてきました。科学的にベッドで過ごすにはどうすればいいでしょうか? 冬が来ました。ベッドは暖かすぎるし、外の空気は寒すぎる。特に、冬になるとすぐに湿気と冷気に襲われ、暖房もない南部地域では、「冬は朝起きるのが大変で、空に登るのと同じくらい大変」なのだそうです。 同時に、冬はさまざまな心臓血管疾患や脳血管疾患の発生率が高い時期でもあり、特に12月から翌年2月までの最も寒い3か月間に多く発生します。午前5時から午前9時の間に急に起きると、体内の血液供給が不足し、起立性低血圧、動悸、失神などの症状を引き起こす可能性があります。 したがって、冬の朝に科学的にベッドで過ごす方法を知ることが重要です。科学的にベッドに留まりたい人のために、いくつかの提案をご紹介します。 1 十分な睡眠時間を確保し、夜更かしを避ける 遅く寝たり、夜更かししたり、長期間十分な睡眠をとらなかったりすると、体の免疫システムのバランスが崩れ、健康に良くありません。朝起きるのが難しい人は、前日に遅くまで寝て夜更かしすると、翌日起きるのがさらに難しくなります。午後10時頃に就寝し、携帯電話をいじらず、カーテンを閉め、室内の照明を暗くし、心地よい音楽を聴き、瞑想をして、心身をリラックスさせ、できるだけ早く眠りにつくことをお勧めします。 2 起床時の不安を軽減 朝起きられないのではないかと心配する人は多く、3〜5分おきにアラームをたくさんセットします。しかし、翌朝起きられないことを心配しすぎると、前夜の睡眠の質にも影響が出てしまいます。朝起きるのに苦労する代わりに、ベッドで横になる時間を自分に与える方が良いでしょう。 3 ベッドに長くいすぎない 30 分間ベッドに留まることが推奨されます。これは、身体が正常な生理機能を回復するのに有益です。しかし、ベッドに長くいると脳や体の機能が阻害され、再び睡眠状態に入ると覚醒に悪影響を及ぼします。 4 お腹が空いているときはベッドにいないでください お腹が空いているときはベッドに寝たままでいないでください。時間通りに起きて朝食をとることをお勧めします。空腹のままベッドにいると、低血糖、胆石、胃炎、胃潰瘍などの病気を引き起こす可能性があり、健康に良くないからです。お腹が空いたときはベッドに居続けないでください。 5 尿意や便意があるときはベッドに居続けないでください 長時間尿を我慢すると膀胱の弾力性が失われ、腎機能にダメージを与えるからです。便を長時間我慢すると腸や肛門に負担がかかり、痔、心血管疾患、脳血管疾患、下肢静脈血栓症、腰椎椎間板ヘルニア、大腸がんなどのリスクが高まり、便秘の原因にもなります。したがって、尿意や便意を感じたら、時間通りに起きてトイレに行き、膀胱内の尿と直腸内の便を排出しなければなりません。 6 目覚めたらまずベッドの中で体を動かす 朝、しばらくベッドで過ごした後、目が覚めた時に、急いで起きる必要はありません。代わりに、ストレッチをしたり、ベッドの端にしばらく座ったり、首、手足、腰、手首、足首を動かしたりすることで、身体機能や精神状態を覚醒させるのに効果的です。 参考文献 [1]https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsr.14054 著者: 曽新月、人気科学ライター 査読者: 北京天壇病院神経科教授兼主任医師、李静静 |
>>: 海水魚を食べなくても大丈夫ですが、この8種類の淡水魚もDHA補給に良いので超オススメです!
推薦する
なぜ牛乳を一口飲むだけで健康を取り戻せるのでしょうか?母乳について詳しく知る |任光旭
私たちは生まれるとすぐに、食物、微生物、免疫のバランスをとるという非常に重要な選択に直面します。バラ...
ザクロを絞ってジュースにできますか?種子をどう処理すればいいですか?ザクロは冷蔵庫で新鮮なまま保存できますか?
ザクロの花は大きくて色鮮やかで、開花期は小麦の収穫期頃から10月までと長いです。ザクロの果実は鮮やか...
痛風患者に朗報です!中国の科学者がコルヒチンの前駆体の合成に成功!痛風治療の「小さな専門家」として知られる
研究チームはコルヒチンの前駆体の合成に成功。痛風患者にとって朗報こんにちは、中国科学普及協会の皆さん...
目立たない調理習慣が家族全員の骨粗しょう症を引き起こす可能性がある
骨粗しょう症に関して、多くの人がまず考えるのはカルシウム補給です。骨粗しょう症の予防のためにカルシウ...
気と血を補給し、老化防止にもなる、女性に最も栄養のある食品トップ10!
正しい食べ物を摂取することで、私たちは内側から健康になり、花のように咲き誇って美しくなることができま...
ぎらぎらとひょろひょろとちかちかの魅力:みんなのうたの新たな輝きを評価する
「ぎらぎらとひょろひょろとちかちか」 - みんなのうたの歴史的作品 「ぎらぎらとひょろひょろとちかち...
唐代オペラの特徴は何ですか?中国オペラの最初の歴史は
中国オペラの独特の美的特徴は、包括性、仮想性、標準化です。ギリシャ悲劇やギリシャ喜劇、インドのサンス...
甘酢スペアリブには、砂糖と酢のどちらを先に入れるべきですか?甘酸っぱいスペアリブに最適な酢は何ですか?
甘酸っぱいスペアリブは、多くの人に愛される家庭料理です。甘酸っぱいスペアリブは夏でもご飯によく合う一...
目の下のクマをどうしたら治せますか?
著者:劉静清、深セン人民病院主治医査読者: 深セン人民病院主任医師 李宇目の周りのくまは、科学的には...
ぼのぼの:癒しの世界と深遠なテーマの魅力的な探求
ぼのぼの - ボノボノ - の魅力と評価 ■公開メディア TVアニメシリーズ ■原作メディア 漫画 ...
間違った「炭水化物」を選ぶと、すぐにお腹が空いて太りやすくなります。
最近、世界保健機関(WHO)は、より科学的で健康的な食生活のアドバイスを国民に提供するために、健康的...
炊飯器の焦げ付き問題を解決する方法(炊飯器の焦げ付きの原因と解決策)
一般的なキッチン家電である炊飯器は、私たちに便利さとおいしさを提供してくれます。それは私たちにトラブ...
インフルエンザの合併症による健康への潜在的な脅威はどの程度ですか?
48歳の女優バービー・スー(大S)と41歳のメディア関係者ン・ユーヤンがインフルエンザで亡くなった...
霊芝を水に浸すとどんなメリットがありますか?霊芝の食べ方と禁忌
日常生活では、多くの友人が霊芝をスライスして、蓮の実、ユリ、ナツメ、ミカンの皮などの材料と一緒に調理...