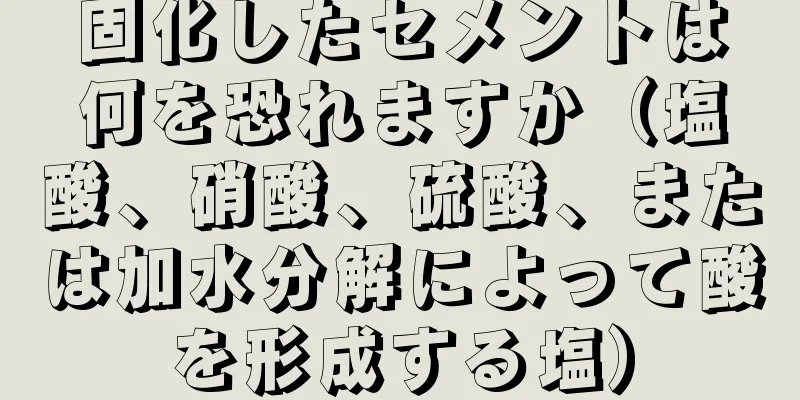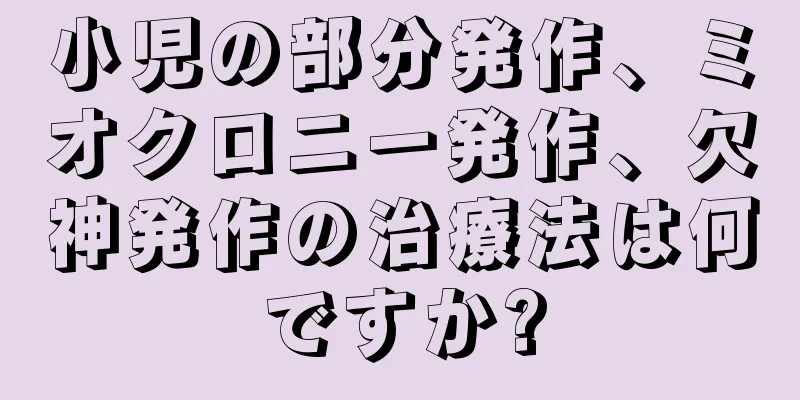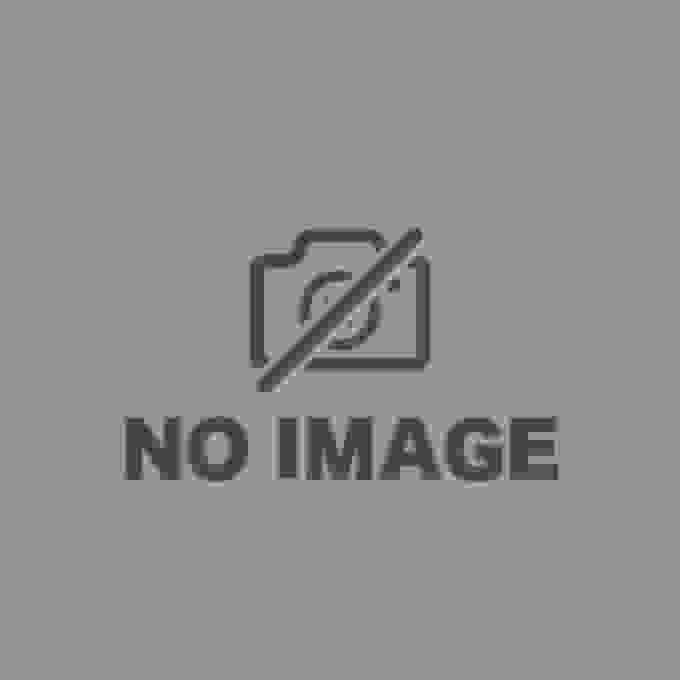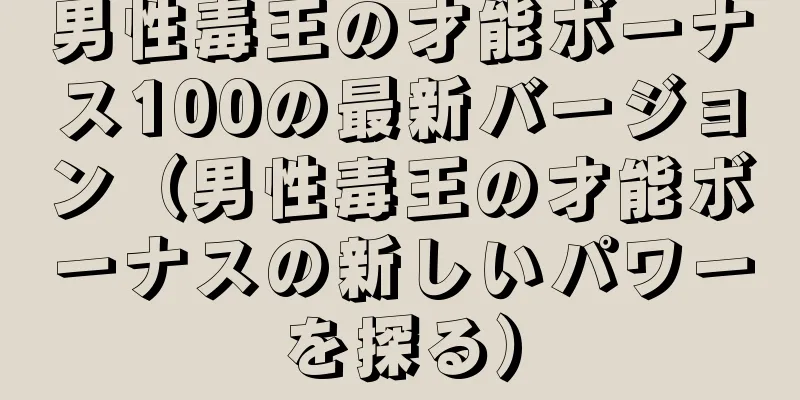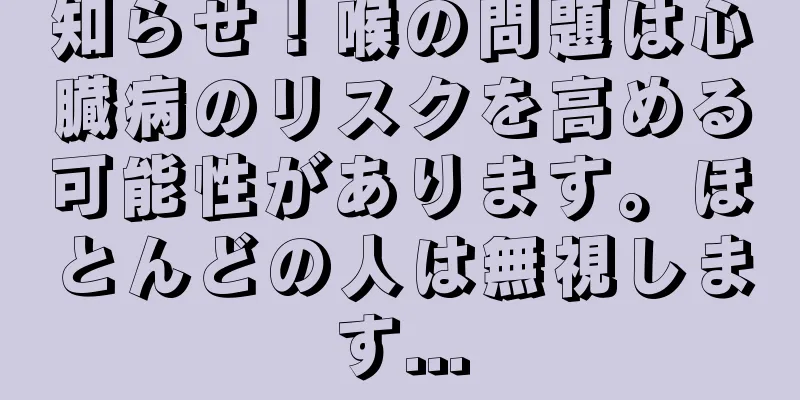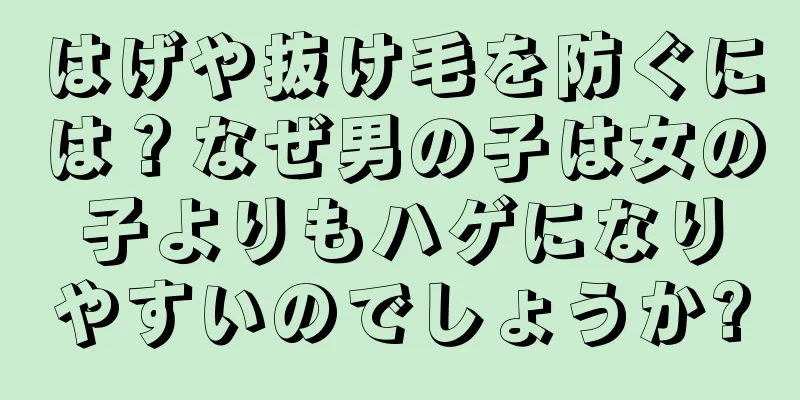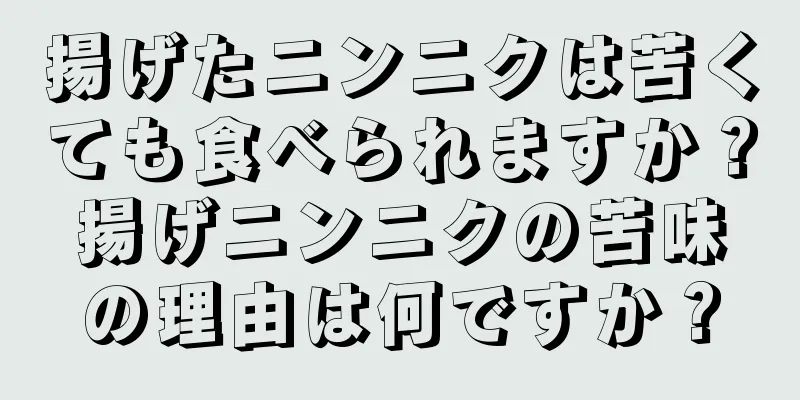卵チャーハンはなぜ粘つくのでしょうか?卵チャーハンをべたつかせずに作るにはどうすればいいですか?
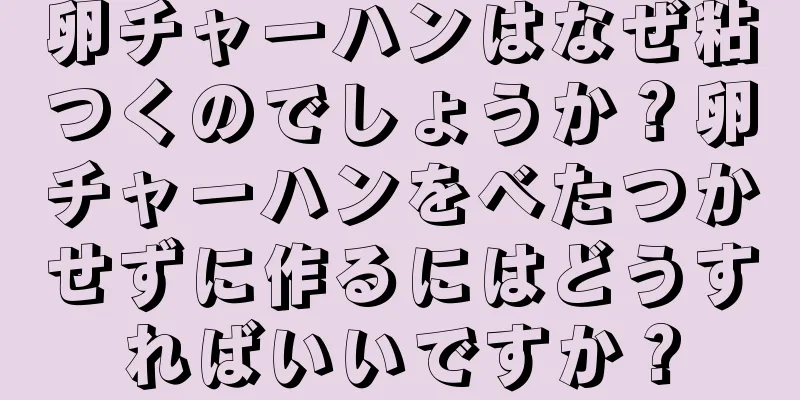
|
卵チャーハンが人気の米の調理法であることは皆さんご存知でしょう。調理法も多彩で、食材も豊富、味も美味しいです。人々に深く愛されています。卵チャーハンを頻繁に食べる人は多いです。卵チャーハンの作り方はとても独特です。チャーハンをベタベタにしてしまう人もいます。では、なぜ卵チャーハンは粘り気があるのでしょうか?以下で詳しく見てみましょう! 卵チャーハンはなぜベタベタするのでしょうか?卵チャーハンがべたべたして卵の風味がなく、魚臭ささえあるのは、基本的に次の 2 つの操作によるものです。 一つは、炊きたてのご飯を炒め物に使うと、すぐにべたついてしまうことです。 2 つ目は、卵液を直接ご飯に注ぐ方法ですが、これも粘り気が出て魚臭くなる可能性があります。 つまり、水分が多すぎると、温度が期待した効果に達しなくなります。水が多すぎると、蒸発し続けます。すると、水分が蒸発して温度が上がらず、自然なカラメル風味が出なくなり、卵自体の生臭さも取れなくなってしまうことがあります。 だから「卵チャーハンには一晩寝かせたご飯を使うのがベスト」というのが一般的な見解となっているのです。これは、一夜漬けしたご飯は水分が比較的少なく乾燥しているため、炊きたてのご飯のような柔らかく香ばしい食感ではなく、冷めた後の方が弾力のある食感になるからです。これにより、特に卵液などの材料と組み合わせると、チャーハンに適したものになります。 べたつかずに卵チャーハンを作る方法卵チャーハンをべたつかせずに作るコツは、 ①使用する米の水分含有量が低いこと。一晩寝かせたご飯がない場合は、ご飯を広げて冷やしたり、冷凍したりして余分な水分を減らすことができます。 ②卵液は直接ご飯にかけない方が良いです。色は良くなり、卵の花とご飯がよりしっかりと密着しますが、火加減の調節が難しいです。長く炒めすぎるとパサパサになり、炒め不足だとご飯がベタベタになったり、卵液の魚臭さが出たりすることがあります。 卵チャーハンの重要なヒント1. 粘り気の問題を解決するために最も重要なことは、スクランブルエッグを作るときに、水分が多く粘り気のある米を使わないことです。粘り気が強い場合は、冷蔵庫に一晩入れてください。冷蔵庫で一晩置くと米の水分が吸収され、チャーハンの粒がはっきりした状態になります。 2. 一晩置かずにすぐに揚げたい場合は、米に片栗粉や塩をまぶして水分を吸収させましょう。こうすることで乾燥し、くっつかなくなります。 3. キノコを加えると風味が増し、ベーコンを加えると塩味と新鮮さが増し、トウモロコシの粒を加えると甘味が増します。もちろん、ご自身の好みに合わせてお選びいただくことも可能です。 4. いわゆる中華鍋の熱とは、ご飯が鍋の中にくっつくまでの 2 ~ 3 秒を指します。これにより、高温下で米やさまざまな材料が均一に加熱されます。 5. 卵に少量の料理酒を加えると、魚臭さがなくなり、揚げたときに卵がよりふわふわで柔らかくなります。 |
<<: 新鮮なサンマはどんな見た目ですか?新鮮なサンマかどうかはどうやって見分けるのでしょうか?
>>: 卵チャーハンに最適な米はどんな米ですか?卵チャーハンに最適な米はどんな米ですか?
推薦する
出産後はなぜ便秘になりやすいのでしょうか?通常出産時の便秘を解消するにはどうすればいいですか?
出産は身体的に負担の大きいプロセスであり、出産後の産褥期間中は母親にとって多くの問題が生じます。例え...
新型コロナウイルスによる「白い肺」や心筋炎は本当に若者や中高年の隠れた死因なのか?
新型コロナウイルスに対する国民の主な不安は、これまで高齢者や在宅病人に向けられてきた。しかし最近、ソ...
仕事に行きたくない、食欲がない…また「休日後症候群」に悩まされていませんか?完全に健康になって復活するためのコツを教えます!
長い休暇から仕事に戻るときは元気いっぱいでなければならないとよく言われますが、仕事の最初の 1 週間...
iPhone 7とiPhone 7 Plusに大きな違いはある?(iPhone 7 Plusのメモリ容量の違いを詳しく解説)
今日はiPhone 7とiPhone 7 Plusの比較を皆さんと共有します。多くの友人がApple...
SSD 4Kアライメントの重要性と設定方法(SSDのパフォーマンスと寿命を向上させるための重要な手順)
ソリッド ステート ドライブ (SSD) は、多くのユーザーに好まれるストレージ デバイスとなってい...
科学的な食事療法は腎臓病の進行を遅らせるのに役立ちます - 慢性腎臓病患者のための食事ガイドライン
【編集部注】習近平総書記の中医学に関する重要な講演を研究・実行し、「中医学の継承と革新を推進し、中医...
ポピュラーサイエンス:近視手術中に「事故」が起こったらどうすればいいでしょうか?
人の想像力がどれほど大きいかは決して分からない。例えば、近視の手術に関して、手術中に誤って瞬きをした...
GWI: 2021年ソーシャルメディアトレンドレポート
GWIは「2021年ソーシャルメディアトレンドレポート」を発表し、ソーシャルメディアは2020年にそ...
『電波教師』の魅力と評価:個性的な教師と生徒たちの物語
『電波教師』:異色の教師と生徒たちの成長物語 『電波教師』は、東毅による同名の漫画を原作としたTVア...
妊娠36週で胎児の頭が小さい場合はどうすればいいですか?羊水を補うために何を食べたらいいですか?
妊娠中は、胎児の発育と健康状態を確認するために定期的な出生前検診が行われます。 B超音波やその他の方...
背の高い人は腰椎椎間板ヘルニアになりやすいのでしょうか?
噂:「背の高い人は体にかかる負担が重く、腰椎椎間板ヘルニアになりやすい?」一部のネットユーザーは、背...
もち米団子を作るのに最適なものは何ですか?もち米に混ぜて食べてはいけないものは何ですか?
もち米団子は湯団子とも呼ばれ、漢民族の伝統的な軽食の代表の一つです。同時に、中国の伝統的な祭りである...
iPhone 12でデュアルSIMモードを設定する方法(ワンステップ操作、デュアルSIMライフの利便性を享受)
モバイル通信技術の急速な発展に伴い、2枚のSIMカードを同時に使用する必要があるユーザーがますます増...
寒い空気が来たときに風邪をひいてしまったらどうすればいいですか?これらの食べ物を試してみてください!
最近は寒気が頻繁になり、気温も下がり、風邪をひく人も大幅に増加しています。しかし、風邪の症状が出た後...
『愛馬の行方』レビュー:感動の結末とキャラクターの成長を徹底解説
愛馬の行方 - アイバノユクエ 「愛馬の行方 - アイバノユクエ」は、1933年1月1日に公開された...