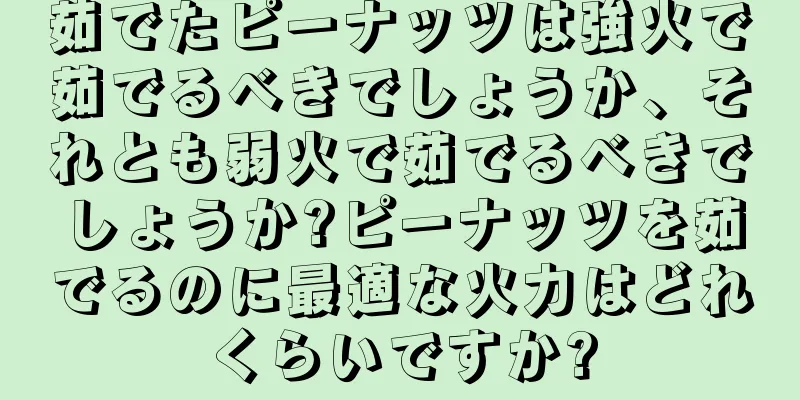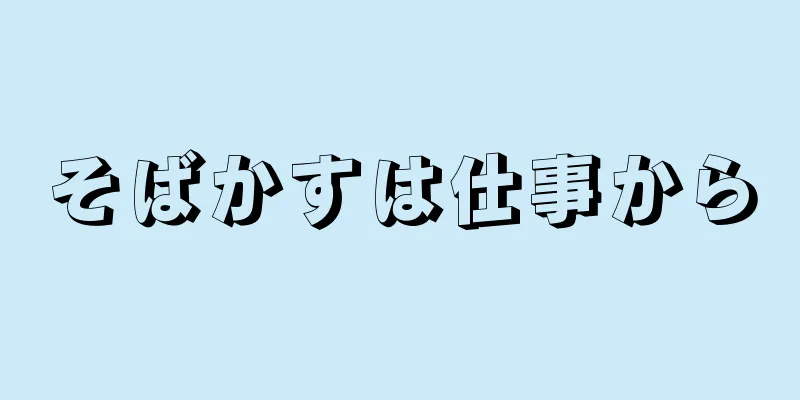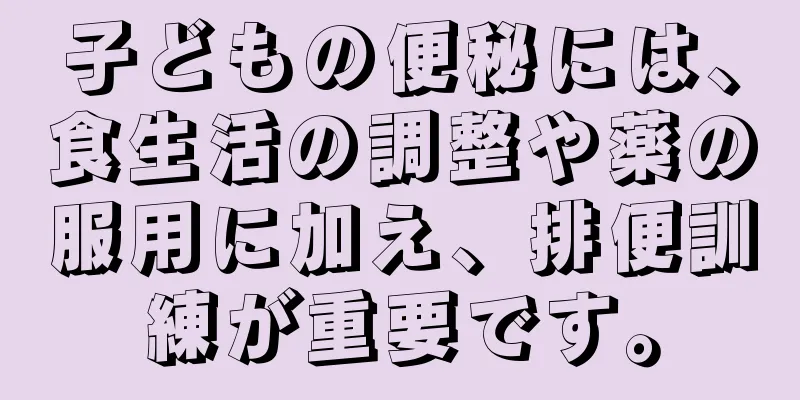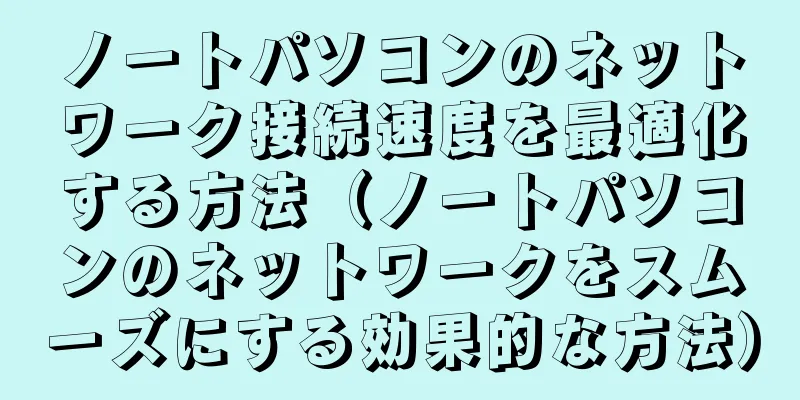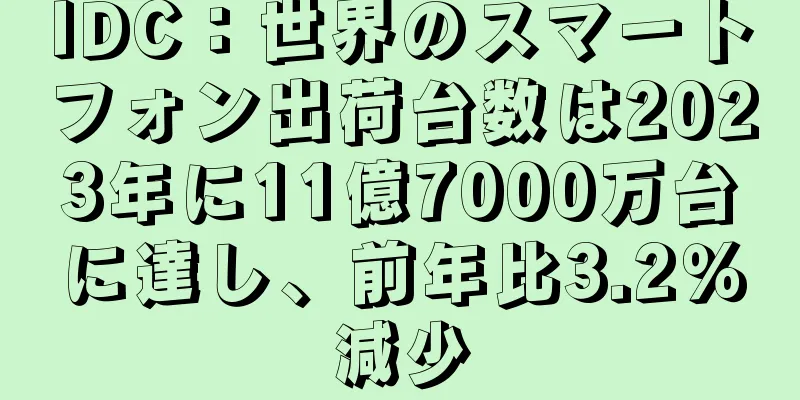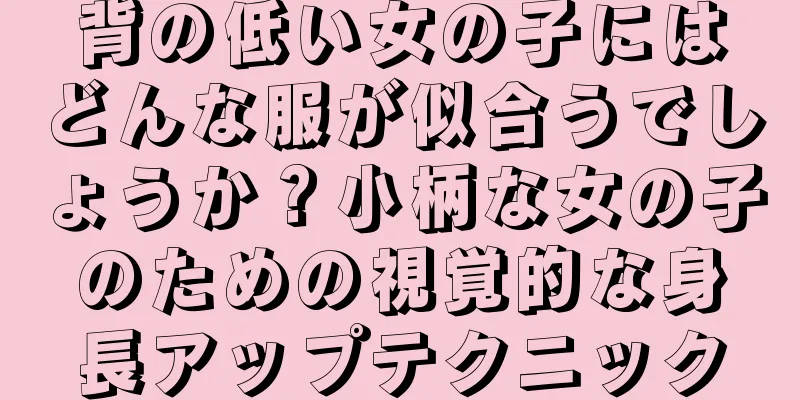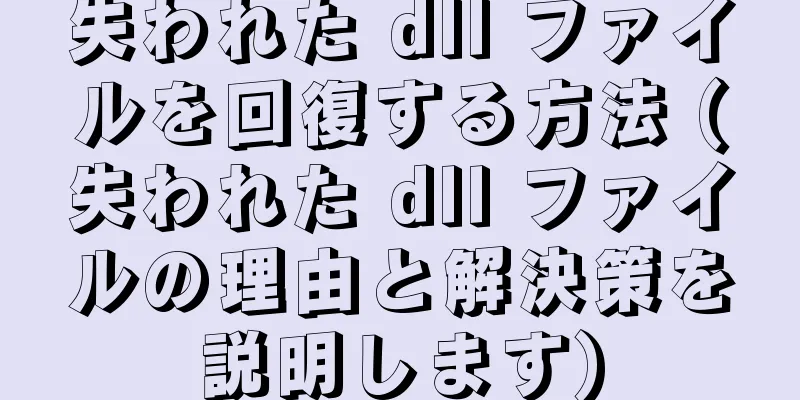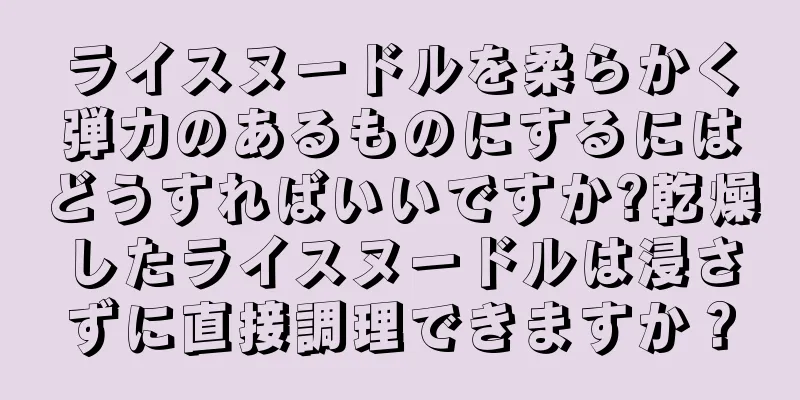食道を守るために、私から始めましょう
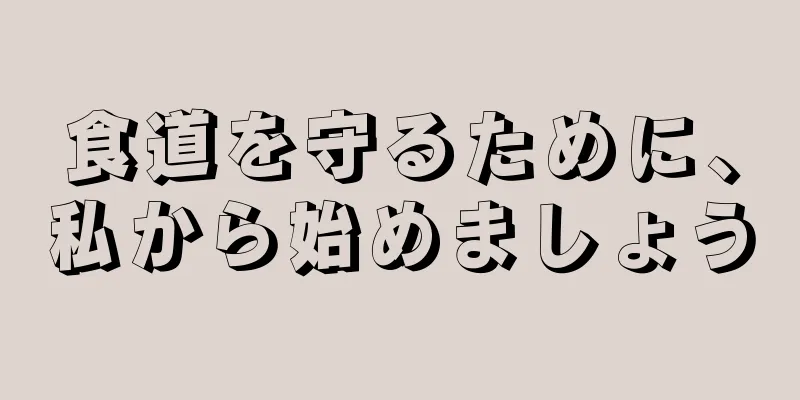
|
中国語ネイティブとして 私たちは子供の頃から中国文化の影響を受けてきました。 冷たい食べ物を食べるのは良くないと思う だから私たちは主に温かい食べ物を食べます。 飲料水は熱くなければならない 食べ物は温かくなければなりません。 私たちは常に温度の魔法を信じてきました 食品の色、香り、味を誘発するだけでなく 食欲を増進し、食物の消化と吸収を促進することもできる。 しかし、温かい食べ物はどうでしょうか? 熱すぎると それで何が起こるでしょうか? 食道は、食べ物を口から胃へ運び、さらに消化させる長い筋肉の管です。しかし、すべての「管」には有効期限があり、食道も例外ではありません。不適切に使用すると、食道に損傷を与えたり、壊死を引き起こしたりすることがあります。食道の「老化」には多くの原因がありますが、最も重要なのは高温です。一般的に、人体に適した食品の温度は10℃~40℃であり、この温度帯を「熱い」と呼んでいます。私たちの食道は40℃から60℃の温度に耐えることができますが、65℃を超えると火傷とみなされます。 食道の表面は粘膜層で覆われており、安全な温度を超える食品に触れると火傷を負います。火傷がたまに起こるだけであれば、すぐに自然に治ります。しかし、沸騰した熱い食べ物による刺激が長時間続くと粘膜病変を引き起こし、表面の炎症や潰瘍から悪性増殖へと変化し、食道がんのリスクが高まります。 中国では、65℃または70℃以上の水、コーヒー、お茶を飲む習慣があり、それに応じて食道がんのリスクが高まることが報告されています。国立がん登録センターの最新の統計によると、中国では食道がんの発生率が40歳を過ぎると急激に増加する。そのため、食道がんは「中国特有のがん」と揶揄されることがあります。まず、中国での発生率は高いです。第二に、食道がんは中国では古くから存在しており、一般的に横隔膜疾患として知られています。 嚥下障害とは、食べ物を飲み込むときに詰まってしまう、食べ物を飲み込みにくい、食べ物を逆流させてしまうなどの症状をいいます。伝統的な中国医学では、嚥下障害は食道にあり、胃によって制御され、肝臓、脾臓、腎臓に関連していると考えられています。したがって、食事の要因に加えて、感情的な欲求不満、長期の病気、高齢などが窒息の発生につながる可能性があります。 諺にもあるように、「賢者は既存の病気を治療するのではなく、病気が起こらないように予防する」のです。窒息を防ぐために何ができるでしょうか? まず第一に、私たちは悪い食習慣を変える必要があります。食べる前に、食べ物を安全な温度まで空気乾燥させる必要があります。喫煙や飲酒もやめ、漬物や残り物もやめましょう! 第二に、新鮮な果物や野菜をもっと食べるべきです。 最後に、定期的に病院に行って身体検査とスクリーニングを受ける必要があります。なぜなら、現時点では食道がんを予防し、早期にスクリーニングできる方法は胃内視鏡検査しかないからです。 (インターネットからの写真) 投稿者: Wu Yuan 査読者: Liu Weihong |
<<: 私たちの生活のどこに発がん物質が隠れているのでしょうか?
>>: 長時間座り続ける方必見!見に来てください、あなたは正しい場所に座っていますか?
推薦する
キンカンワインにはどんな栄養価がありますか?黄色い皮の果物の食べ方
キンカンの実はそのまま食べたり、おいしいフルーツスナックにしたり、洗って種を絞り出し、瓶に入れて発酵...
ウマウマラーメンの魅力:みんなのうたから学ぶ感動の味
ウマウマラーメン - みんなのうた 「ウマウマラーメン」は、1991年10月にNHK教育テレビ(現在...
陽性反応が出た後、嗅覚や味覚が損なわれた場合はどうすればいいですか?嗅覚と味覚を素早く回復させる5つのヒント
コーヒーの香り:ある外国では、コーヒーの香りがCOVID-19患者の嗅覚に与える影響について実験が行...
秋に健康を維持するための秋の健康的な食事ガイド
諺にあるように、秋は実りの季節であり、秋の食べ物も多様です。秋の特徴と人々の身体的なニーズを考慮して...
KindleでWeChat Readingを使用する手順(読書体験をより便利にする)
現在、WeChat Readingは人気の電子書籍プラットフォームであり、Kindleは多くの人にと...
隠された iPhone アプリ アイコンを取得する方法 (失われたアプリ アイコンを取得するシンプルで簡単な方法)
iPhoneは非常に人気があり、現代の携帯電話は私たちの生活に欠かせないものとなっています。ただし、...
どれくらい眠らずにいられますか?
1963年、17歳のランディ・ガードナーは、カリフォルニアの高校の科学フェアのプロジェクトで11日...
『RELEASE THE SPYCE』スパイ少女たちの活躍を徹底評価!
RELEASE THE SPYCE - リリース ザ スパイス - レビューと推薦 ■公開メディア ...
液体コンドームの使用感はどんな感じでしょうか?液体コンドームを使用した後は性器を洗う必要がありますか?
液体コンドームは女性向けに特別に設計されています。裸挿入でも安全性を確保でき、潤滑機能も内蔵していま...
インフルエンザを予防するには?これらのヒントを守ってください
1. インフルエンザとは何ですか? Fluはインフルエンザの略語です。風邪とは異なり、インフルエンザ...
肝臓は私たちにとってどれほど重要なのでしょうか?肝臓の運命を見てみましょう
著者: Sun Yuhang および Zhou Yixi Medical Collegeイラスト:孫...
パーキンソン病の初期症状は手の震えだけではない
□ 王明宇毎年4月11日は世界パーキンソン病デーです。この日は、英国の医師ジェームズ・パーキンソン博...
オヨネコ ぶーにゃん - 魅力的な猫キャラクターとストーリーの深みを徹底評価
オヨネコ ぶーにゃん - 懐かしのギャグアニメを振り返る 1980年代の日本アニメーション界において...