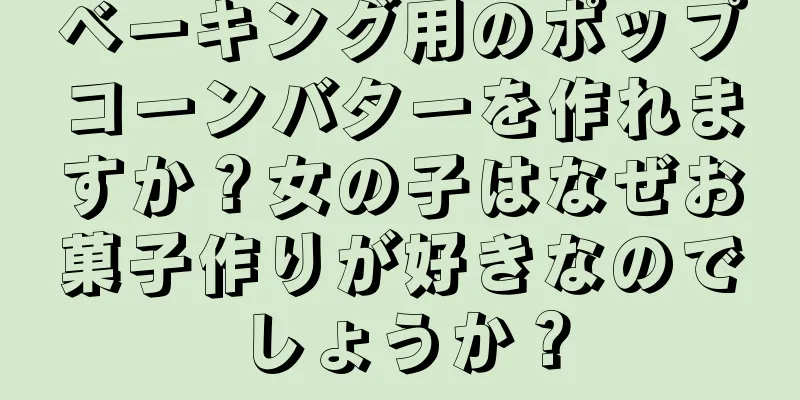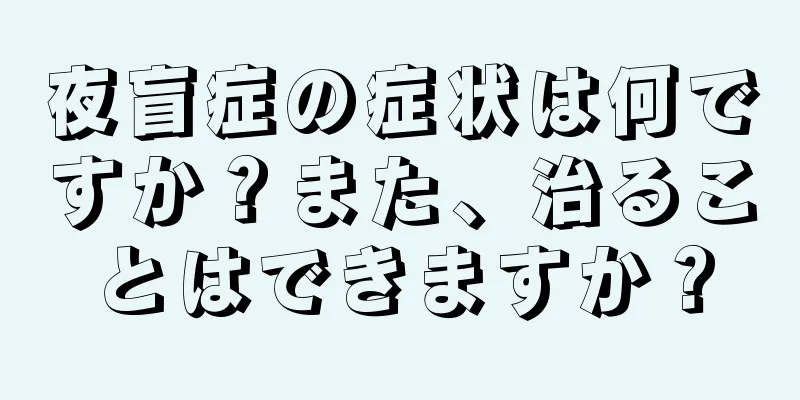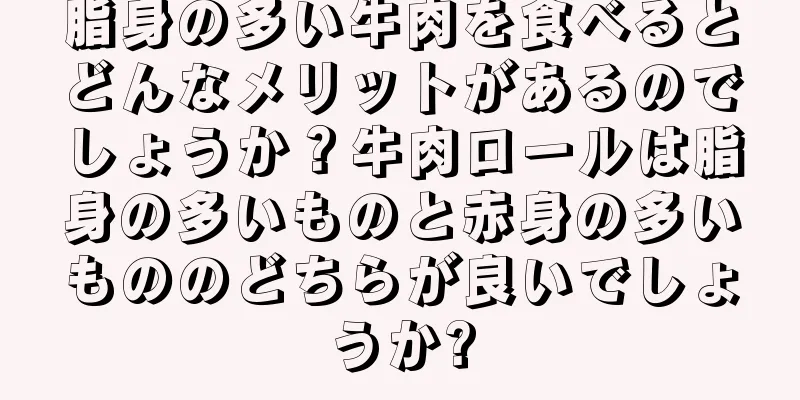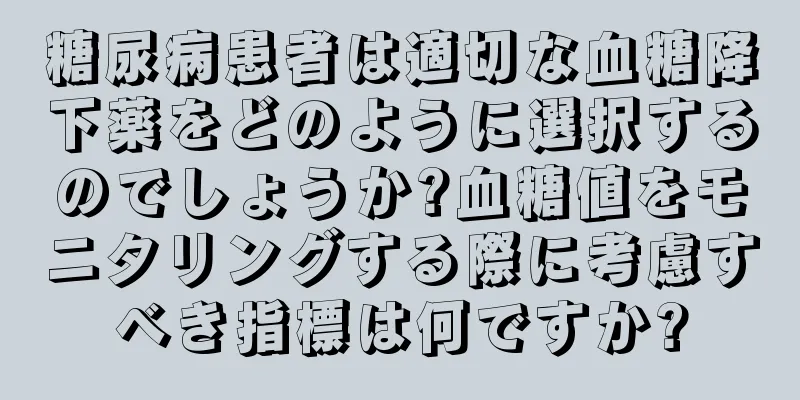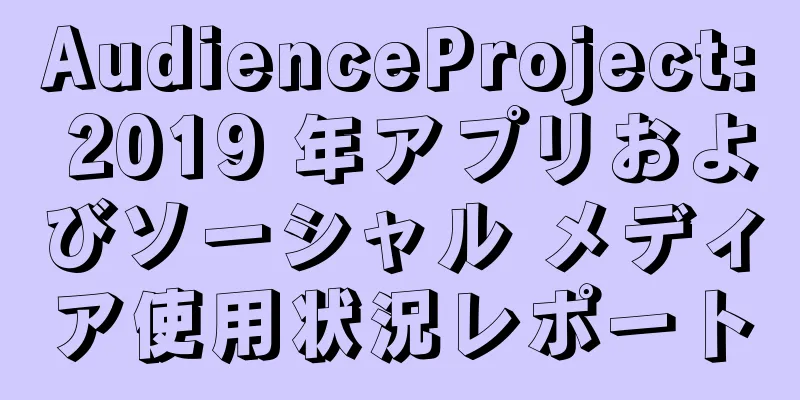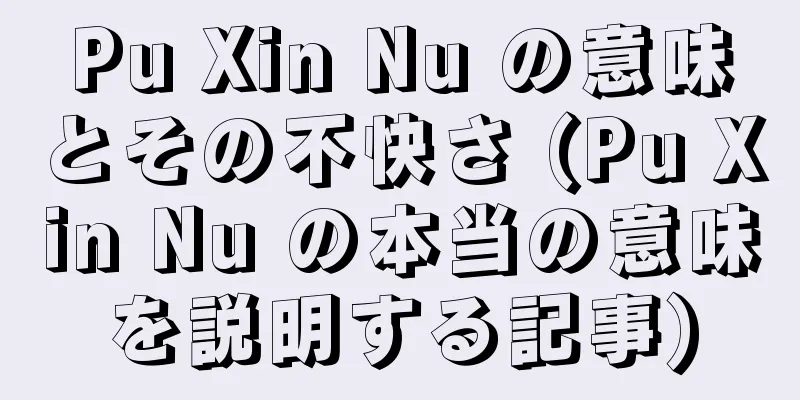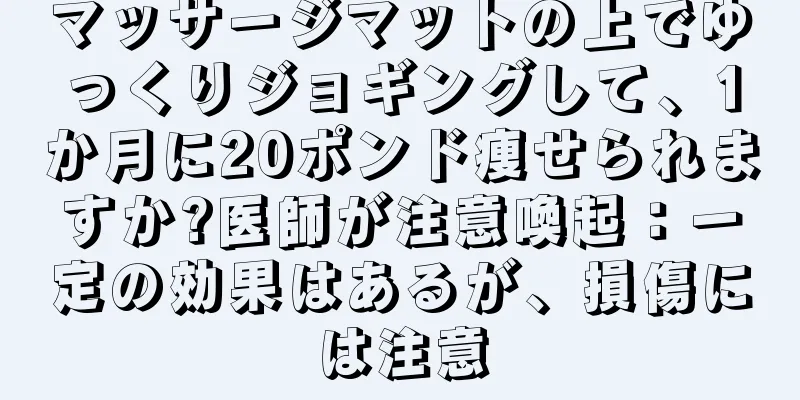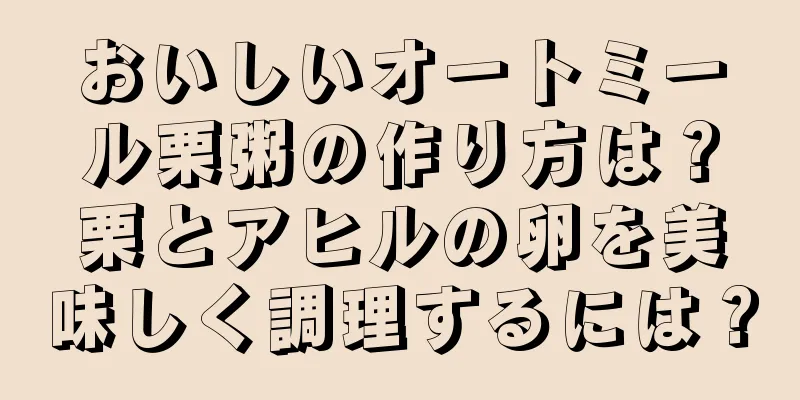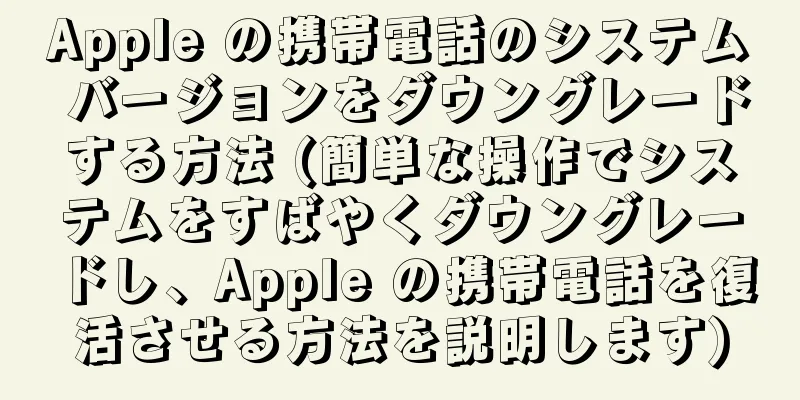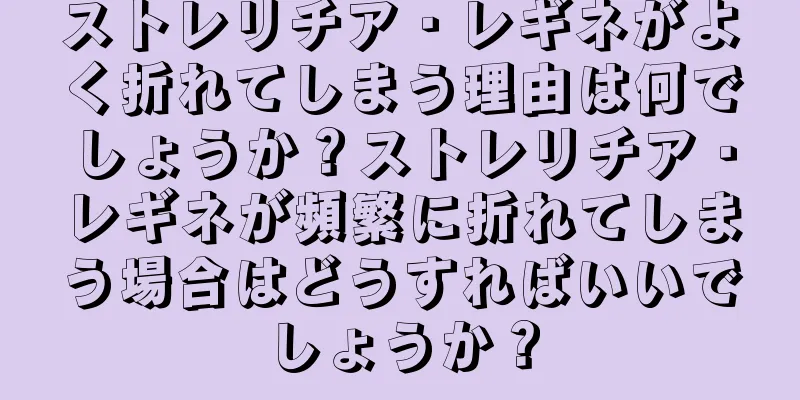女性科学公開授業 |小中学生とその保護者、北京協和医学院の有名医師らが近視の予防と管理について語る
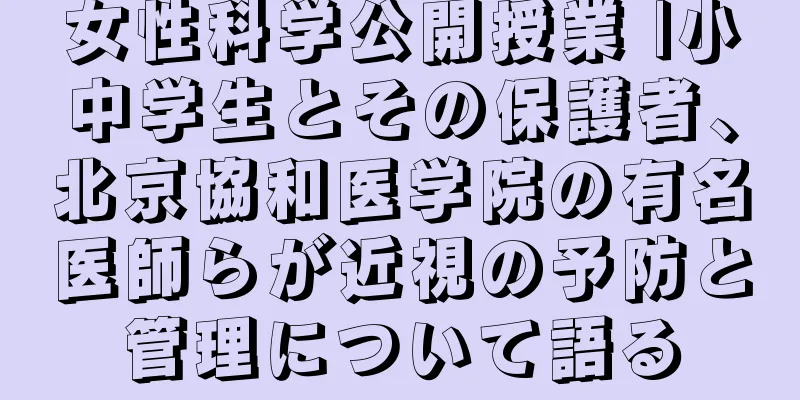
|
携帯電話、コンピューター、その他の電子製品は子供や若者の間で広く普及しており、「小さなメガネ」の数も増加しています。国家衛生委員会が発表した最新のデータによると、わが国の児童・青少年の近視率は全体で52.7%です。 近視の予防と制御の状況は厳しいです。個人にとって、メガネをかけることは不便なだけでなく、メガネによって「美しい顔」が封印されるため、目を保護することが重要です。 今回の「女性科学公開授業」では、北京協和医学院病院の眼科教授で博士課程の指導教員である李慧氏を特別に招き、学生に向けて「青少年の近視予防と制御戦略」について講義していただきました。 近視を予防し、コントロールする方法をお教えします。 ▶ 小学校は近視予防とコントロールの「黄金期」 小学生段階(6~12歳)は近視予防とコントロールの黄金期であり、6~9歳は黄金の中のダイヤモンド期です。視力は正常だが近視のリスクが高い、または遠視の予備力が不十分な生徒については、早期の予防と集中的な介入を行う必要があります。 近視を防ぐための 3 つのステップ: 目の動作、適切な照明、屋外での活動。 健康的な目の習慣を養う 科学的な目の使用と目の保護に関する知識を理解し、20-20-20 ルールを遵守してください。 つまり、電子製品を 20 分間見た後、少なくとも 20 秒間、20 フィート (6 メートル) の距離を見つめます。これにより、眼精疲労を効果的に予防し、近視の進行を抑えることができます。 学生の学業負担を軽減するために屋外活動や運動を強化する。子どもや青少年に、目の衛生習慣を身につけさせ、目を大切にし、目を守る行動を確立するよう促します。 · 視覚的に健全な環境を構築する 家庭や学校は、生徒の宿題や課外活動の負担を軽減し、照明環境を改善し、子どもや青少年の身長に合った机や椅子を備えるべきである。メディアとコミュニティは、関連する基準と知識に関する宣伝を増やす必要があります。支援的な社会環境を作りましょう。 日中の屋外活動を増やす 学校、家庭、地域社会が協力して、児童・青少年の長期的な近視を軽減し、さまざまな対策を講じ、児童・青少年に適切な条件を提供し、屋外活動を行うよう促します。 1日2時間以上。 ▶ 近視を早期にコントロールすればするほど、その効果は大きくなります 近視に影響を与える主な要因は 2 つあります。 一つは遺伝的要因です。強度近視の場合、遺伝的要因はより明白です。軽度および中等度の近視は、遺伝と環境の複合的な影響によって引き起こされます。親が近視である青少年の近視リスクは大幅に増加し、親の近視の程度と正の相関関係にあります。 2つ目は環境要因です。近距離での目の過度の使用、屋外活動の不足、読書や書き物の習慣、照明や栄養、睡眠時間、微量元素、電子製品の使用はすべて、小児および青少年の近視の発生率が高い主な原因です。 データによると、2020年には6〜8歳の子供の近視率が大幅に増加しました。近視の発症年齢が若いほど、平均進行速度は速くなります。調査の結果、7歳児の平均的な進歩は11歳児のほぼ2倍であることがわかった。 7 歳または 8 歳で近視を発症した子供のうち、介入がなければ 53.9% が成人後に強度近視を発症します。強度近視は視力喪失の主な原因の一つとなっています。 近視を早期にコントロールすればするほど、その恩恵は大きくなります。最終的な目標は、近視が急速に進行する年齢での近視の進行速度を低下させ、それによって強度近視の発生率を低下させることです。 したがって、すでに近視になっている小児および青年の場合、医療機関に行って検眼やその他の屈折検査を受け、明確な診断を下し、適時に矯正措置を講じることが推奨されます。 ▶ 近視の進行を抑えるには? 小児の近視の進行を遅らせる方法は、薬物による制御と光学的介入の 2 つです。 薬物による制御は、小児および青少年の近視の予防と制御において専門家によって達成されたアトロピン点眼薬の使用です。研究により、0.01%アトロピン点眼薬は近視の進行を遅らせる効果があり、投薬中止後のリバウンド効果は最小限で、近視抑制に累積的な効果があることが確認されています。 最初の光学的介入は眼鏡をかけることです。眼鏡をかけると子供の近視が悪化するのではないかと心配する人は多いです。それは誤解です。適切な度数の眼鏡を適時に着用すると、鮮明な視界が得られ、近視の進行を抑えることができます。 2つ目は、OKレンズとも呼ばれるオルソケラトロジーレンズを着用することです。オルソケラトロジー技術は近視を抑制する強力な手段ですが、医師による厳密な評価、包括的かつ慎重な検査、適切な装用が必要です。 つまり、薬物制御+光学的介入という組み合わせの対策により、近視の急速な進行を最大限に抑制できるのです。 ポピュラーサイエンスについてさらに学びたい方は、引き続き女性科学公開授業にご注目ください。 「女性科学公開講座」は、中華全国婦人連合会宣伝部が主催しています。科学の専門家を招き、大学キャンパスや科学教育拠点など関係する場所で科学講座を開催し、青少年の健全な成長や科学知識など一連のテーマを議論し、全国の小中学生や保護者、家族に広く普及させることを目的とします。 次に、「女性科学公開講座」では、より権威のある専門家を組織して小中学校の校内や街頭などの場所を訪れ、青少年の健全な成長、航空宇宙、科学知識などに関する一連のテーマの講義を行う。講義の過程は一連の科学講座に記録され、全国の小中学生と保護者に配布され、誰もが積極的に科学知識を学び、応用し、疑似科学、反科学などの悪い現象に意識的に抵抗し、科学的思想で頭を武装するのを助ける。 出典:中華全国婦女連合会宣伝部 |
<<: 骨盤底超音波検査と産後腹圧性尿失禁:新たな視点からの総合的な治療とケア
>>: この症状は突然目に現れ、高血圧や糖尿病が原因の可能性があります
推薦する
白牡丹茶にはどんな栄養素が含まれていますか?白牡丹茶の選び方
お茶愛好家は白牡丹茶を選ぶ際に注意すべきです。花のつぼみを注意深く嗅いでみてください。香りが強く、は...
赤ちゃんが睡眠中にぐずるのをやめるまでには通常数か月かかります。赤ちゃんが寝ている間にぐずるのを和らげるにはどうすればいいでしょうか?
赤ちゃんは生まれてすぐにさまざまな問題を抱えることが多く、睡眠中にぐずるのは非常によくある現象である...
エンテカビルを使用する際に注意すべき2つの4つのポイントについて、どれくらいご存知ですか?
最初に注意すべき 4 つのポイント: 1. エンテカビルを服用する前後2時間は空腹状態にする必要があ...
ノートパソコンに侵入したゴキブリの対処法(ノートパソコンに侵入したゴキブリに対処する効果的な方法)
ノートパソコンを使用するとさまざまな問題に遭遇することがよくありますが、最も厄介な問題の一つは、ゴキ...
「B型肝炎2ペア半」を段階的に理解する方法をお教えします
著者: ヤン・フェイ、四川省成都第四人民病院査読者: 唐秦 四川省成都市第四人民病院検査部長 四川省...
顧愛玲を30分間泣かせたACL損傷とは何なのか?アスリートにとってそれはどれほど重要ですか?
数日前、顧愛玲は自身のソーシャルメディアプラットフォームに、トレーニング中に負傷したとの更新情報を投...
日中にアロエベラジェルを使用することはなぜ推奨されないのですか?洗わずにアロエベラジェルを顔に塗って一晩経っても大丈夫でしょうか?
アロエベラジェルは非常に一般的なスキンケア製品です。天然タイプと合成タイプに分けられ、どちらも使用可...
冬に最適な保湿クリームはどれですか?冬に最適な水分補給と保湿クリームは何ですか?
肌に栄養を与えるためにフェイシャルマスクを使うことが重要です。フェイシャルマッサージをしましょう。マ...
臭豆腐を食べるとどんな効果があるのでしょうか?揚げ臭豆腐のソースの作り方
揚げ臭豆腐は非常に有名なおやつです。多くの人がそれを食べるのが好きです。臭豆腐は大臭豆腐、毛豆腐とも...
最適なオプションを選択するのに役立つ、推奨されるプロジェクターブランドトップ10(市場調査で判明)
プロジェクターは、今日のデジタル時代において、学術講義、ビジネス会議、ホームシアターなどの場面で欠か...
雷に注意してください!ネブライザーを当てるときに子供が泣くとより効果的ですか?
ネブライザーとは、液体の薬をエアロゾル状に霧化し、それを気道から吸入することで治療効果を得るプロセス...
豆乳と豆乳のどちらが良いですか?豆乳と豆乳パウダーの違いは何ですか?
豆乳は大豆と牛乳の栄養成分を組み合わせた新しいタイプの固形飲料です。繊細な味わい、強い香り、豊富な栄...
寒中三十九日に灸をすえる理由は何でしょうか?冬の最も寒い日に灸をしても大丈夫ですか?
天酒療法は一年で最も寒い時期の39日間が最も適していますが、一年中いつでも行うことができます。三九灸...
aytm: ソーシャル マーケティングの包括的な考察 - データ インフォグラフィック
次の情報ビューでは、ブランドがソーシャル マーケティングに取り組む方法について包括的なガイダンスを提...
Digiday: Instagram マーケティング予算と信頼度調査 2022
Digiday の調査によると、Facebook と同様に Instagram は広告代理店にとっ...