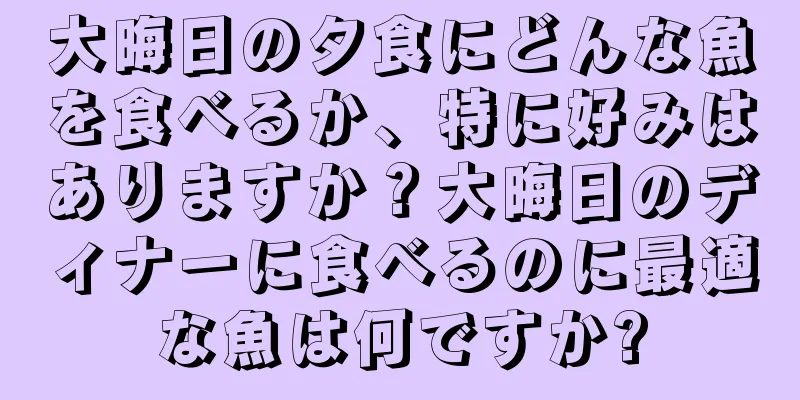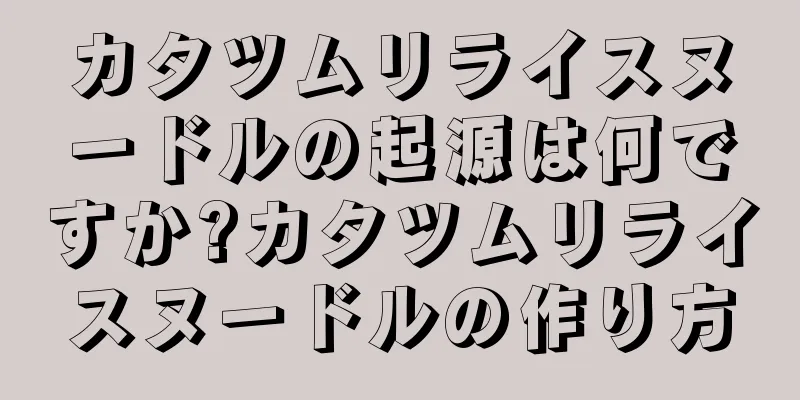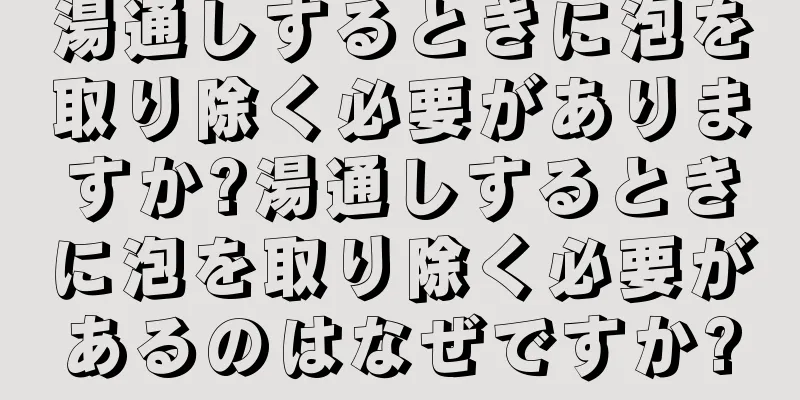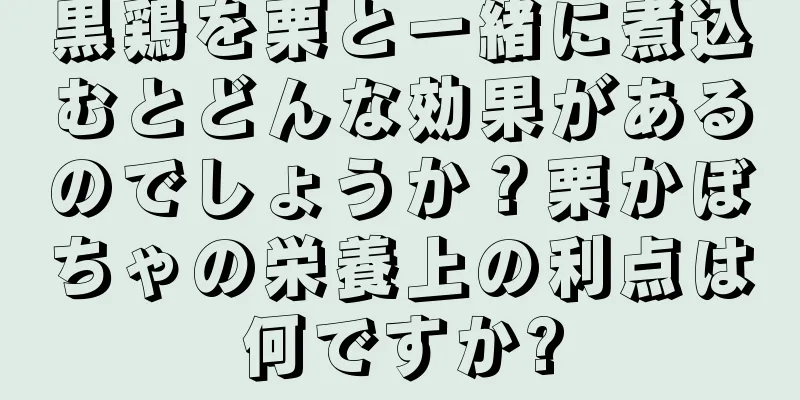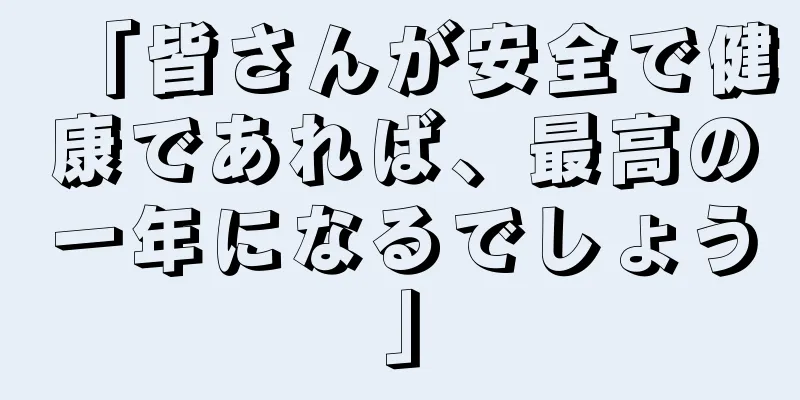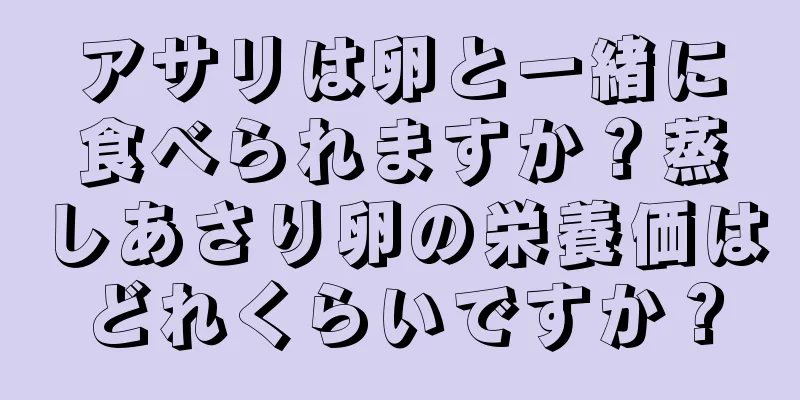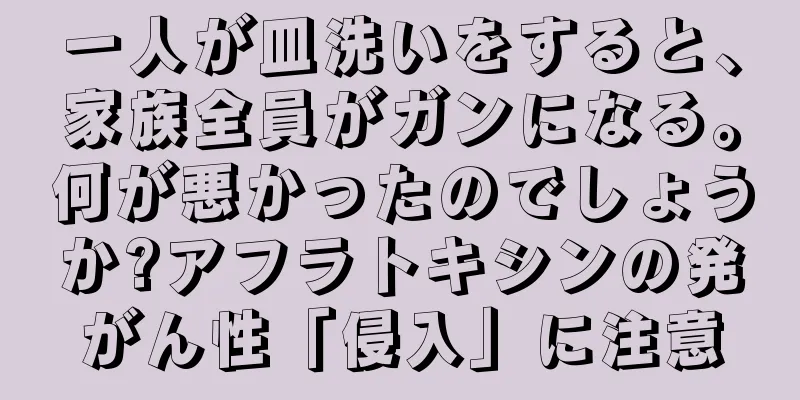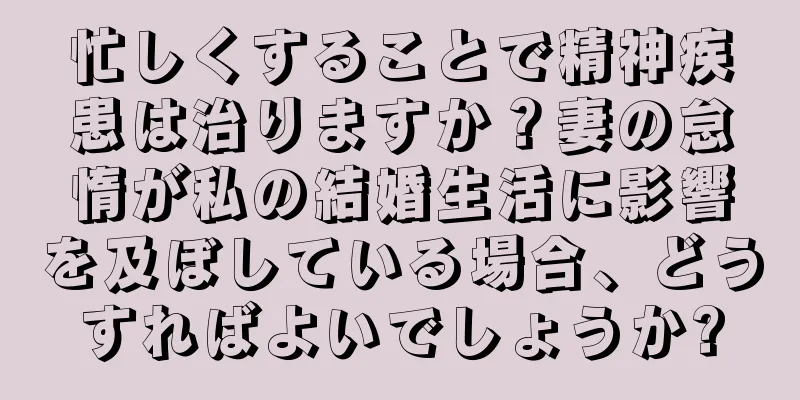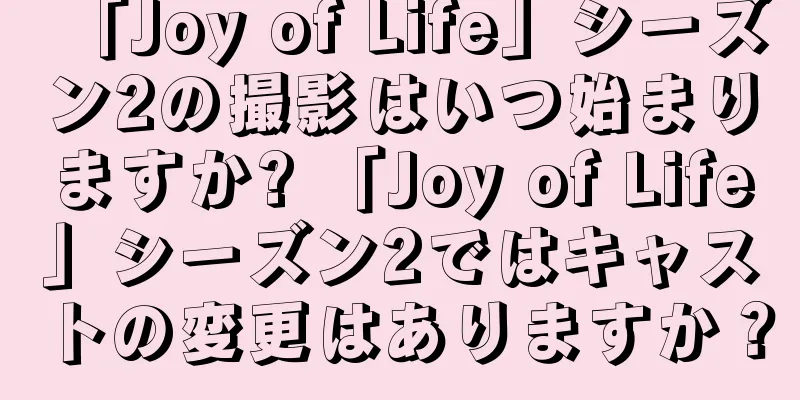目も毎年検査を受ける必要があります。今年はもうやりましたか?
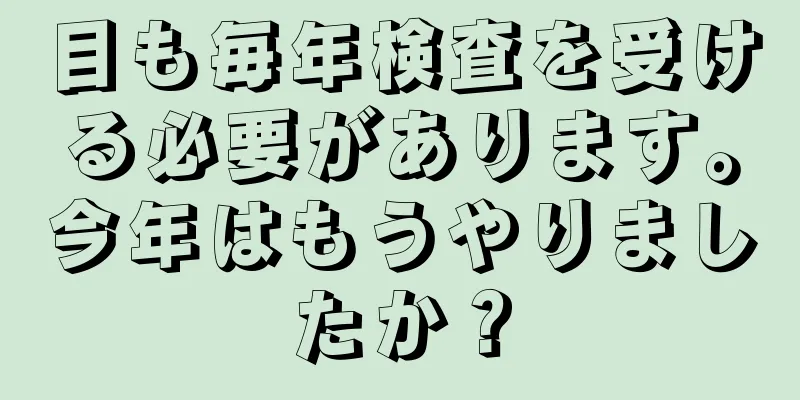
|
年次検査について 車の所有者は 車は毎年点検が必要です 営業許可証には毎年の検査が必要 魂の窓のような目についても同じことが言えます。 特に眼底 年次検査も必要 なぜ眼底にも「年次検査」が必要なのでしょうか? 眼底は、動脈、静脈、毛細血管を肉眼で直接かつ中心から観察できる唯一の身体の部分です。これらの血管は、体の血液循環の動態と健康状態を反映することができます。多くの全身疾患は眼底に反映されることがあります。例えば、眼底出血は糖尿病の重篤な合併症です。高血圧、冠状動脈疾患、腎臓病も眼底に「手がかり」を残します。 眼底疾患には多くの種類があるだけでなく、そのほとんどは視覚機能に重大な損傷を引き起こします。一般の人々は眼底疾患について正しい理解を欠いており、最適な治療時期を逃してしまうことが多く、視力に回復不可能な損傷を与えたり、失明したりすることがあります。病気が早期に発見され、治療できれば、効果はより高くなります。したがって、眼底の年次検査は非常に重要です。 どのような人が毎年眼底検査を受ける必要がありますか? 01.糖尿病患者 糖尿病性網膜症は糖尿病の一般的な微小血管合併症の 1 つです。視力に深刻な影響を及ぼし、失明の4大原因の1つです。 糖尿病の持続期間と血糖異常の重症度が、糖尿病性網膜症を発症する主な危険因子です。そのため、武漢大学付属愛爾眼科病院(愛爾眼科病院グループ湖北総合病院)主任医師、准教授、修士課程の指導教員、湖北省医師会眼科支部副部長、湖北省医師会眼科支部眼底疾患グループ副リーダー、眼底疾患科部長、科長を務める呉建華氏は、次のように提案している。1型糖尿病の患者は、診断後5年以内に眼底検査を受けるべきである。 2 型糖尿病患者は診断後最初の眼底検査を受ける必要があり、病変のない患者は毎年再検査を受ける必要があり、重度の病変がある患者は 3 か月ごとに眼底検査を受ける必要があります。 02.強度近視の人 一般的に、600度以上の近視の目を高度近視と呼びます。眼底に病的な変化が多く見られることから、病的近視とも呼ばれます。高度近視の人の眼軸長は普通の人よりも長くなります。眼軸長が長くなるにつれて網膜は引き伸ばされ薄くなります。網膜変性、網膜剥離、眼底出血などの可能性も普通の人より高くなります。 定期的な眼底検査により、網膜周辺変性、網膜裂孔、網膜剥離につながる可能性のあるその他の状態を早期に発見し、適時に治療して網膜剥離の発生を減らすことができます。そのため、呉建華院長は、強度近視の患者全員に対し、問題が起こる前に予防するために少なくとも年に1回は眼底検査を受けるよう注意を促している。 03. 50歳以上の中高年者 加齢黄斑変性症は、加齢に伴って眼底の黄斑部の構造に生じる変化であり、主に視力低下、視覚の歪み、色覚の変化として現れます。主に 50 歳以上の人に発症します。発症率は年齢とともに増加します。現在、高齢者の失明の主な原因となっています。特に、加齢黄斑変性症の初期症状は明らかではなく、無視されやすく、治療が遅れることがあります。そのため、 50歳以上の中高年者は早期発見・早期治療のために年に1回は眼科検診を受ける必要があります。 04.高血圧の人 高血圧が進行すると、網膜細動脈が硬化します。したがって、眼底血管の変化を追跡することは、高血圧の段階、種類、予後を判断する上で一定の価値があります。特に長期にわたり血圧コントロールを行っても血圧が不安定な方は、少なくとも年に1回は眼底検査を行う必要があります。 眼底疾患を解決する鍵 早期発見と早期治療 定期的に眼科医に眼底検査を受けましょう |
<<: コーヒーを飲むと本当にこんな効果があるの?痛風患者に朗報です!
>>: 徐碩貴教授丨アイアンマンスーツを着ていないと骨折に注意してください!
推薦する
超合体魔術ロボ ギンガイザーの魅力と評価:見逃せない理由とは?
超合体魔術ロボ ギンガイザー - 懐かしの70年代ロボットアニメの魅力 1977年、テレビアニメシリ...
コミック丨豚の告白: 人類を救う計画が私の肩にのしかかるとき!
査読者: 唐 博、中国農業大学分子生物学博士この記事はテンセントの「Everyone Loves S...
WeChat ビデオビューティー機能をオンにする方法 (WeChat ビデオビューティー機能をオンにする方法を説明する詳細な手順)
ソーシャルメディアの発展に伴い、WeChat でビデオチャットやグループビデオ通話をする人が増えてい...
セレンを豊富に含む食品は何ですか?セレンを豊富に含む食品の利点は何ですか?
セレンを豊富に含む食品は、微量元素のセレンを豊富に含む食品です。一般的には、天然のセレンを豊富に含む...
BI: ネイティブ アプリの使用率が依然として HTML5 より高いのはなぜでしょうか?
HTML 5 アプリケーションは、Web ページに基づいて開発され、モバイル ブラウザーで実行され...
Apple 携帯電話の過熱問題を解決する効果的な方法 (Apple 携帯電話の過熱問題の原因と解決策)
モバイルインターネットの急速な発展により、Apple の携帯電話は人々の生活に欠かせないツールになり...
『アフターマン』レビュー:みんなのうたの感動を再評価
『アフターマン』:NHKの短編アニメが描く未来への希望 1994年10月にNHK教育テレビ(現在のN...
DDOS 攻撃は何を破壊するのか (DDOS 攻撃の種類と防御戦略)
1. DDoS とは何ですか?一部のポートがこれらのホストに開かれていないため、これらのホストがこれ...
透析患者は便秘の痛みにどのように対処するのでしょうか?対処法は4つ、集めるのがおすすめ〜
1.食物繊維の摂取を増やす食生活を調整し、水分とカリウムの摂取量をコントロールしながら、野菜、果物...
携帯電話の通話中に相手の声が聞こえない問題を解決する(携帯電話の通話中に音が出ない原因と解決策を解消)
しかし、電話をかけるときに相手の声が聞こえないという問題に遭遇することがあります。携帯電話は私たちの...
ドライアイに関するよくある誤解3つ、今すぐ避けましょう!
ドライアイ症候群は、誰の目にも本当に「少し透明な」病気です。さまざまな複雑な眼疾患の巨大なグループに...
タコを食べるのに最適な季節はいつですか?タコの保存方法
沿岸地域に住んでいる場合、タコは食卓によく並ぶシーフードの珍味です。絹のように柔らかく、肉厚で魚介本...
がん細胞はこれら 5 つの味を好みます。気に入って頂けましたか?
諺にあるように、癌は口から発生します。がんの侵略を避けたいのであれば、がん細胞が最も好む食べ物に特に...
グレーデーツの生育環境はどのようなものですか?グレーの日付を選択するにはどうすればいいですか?
ナツメには、体の免疫力を高める効果があり、気血を補い、血液を養い、神経を落ち着かせる効果もあります。...