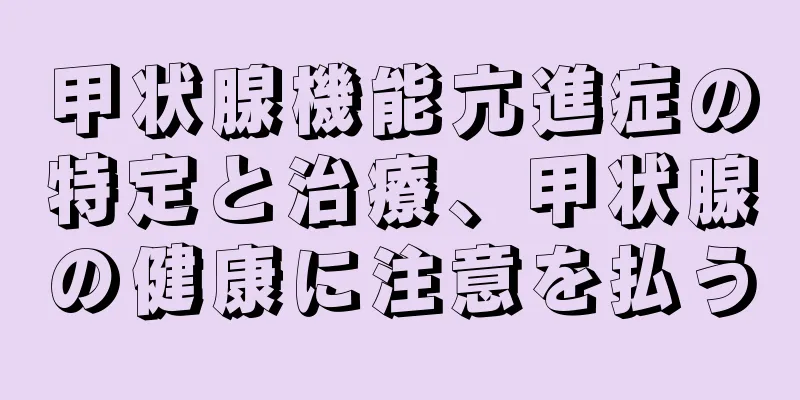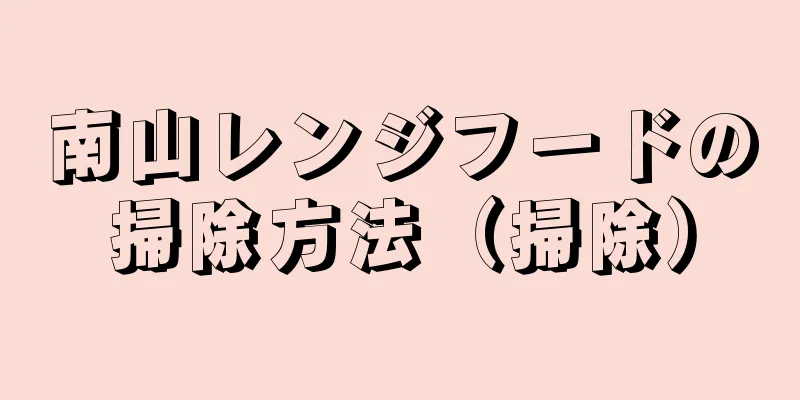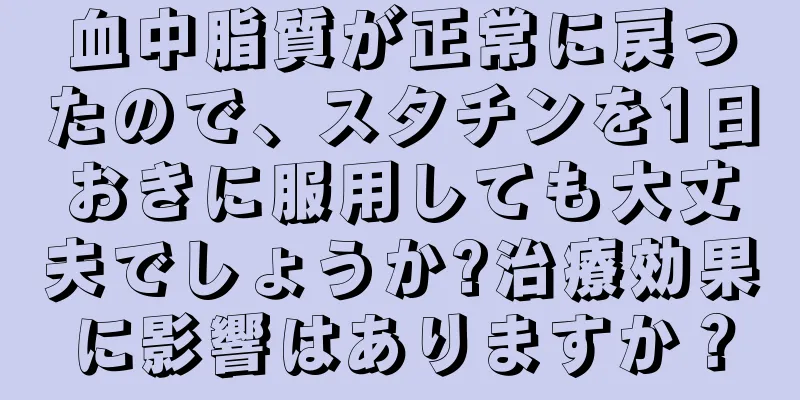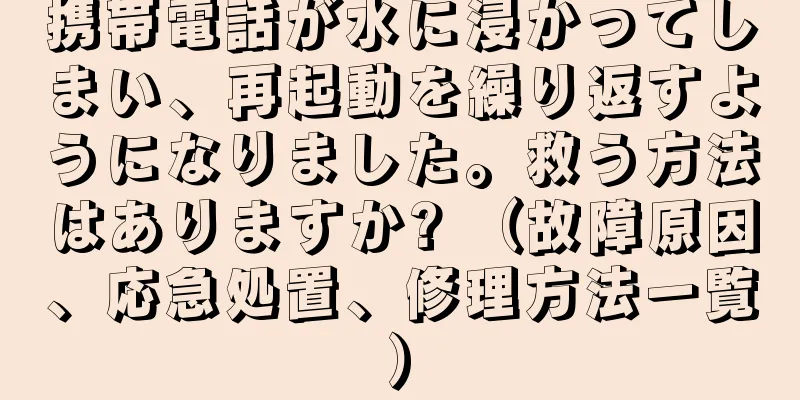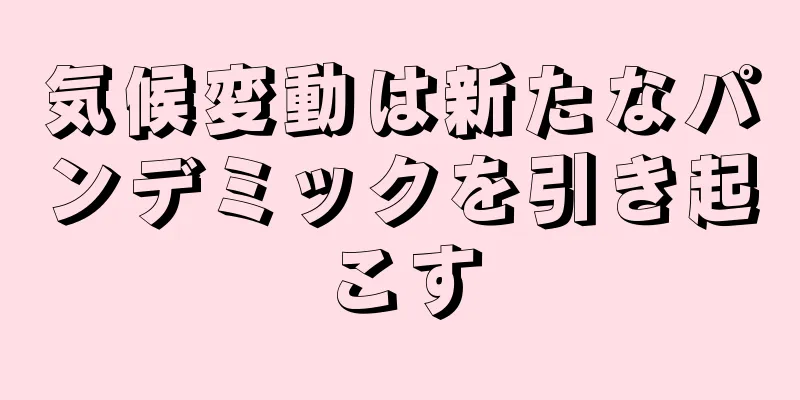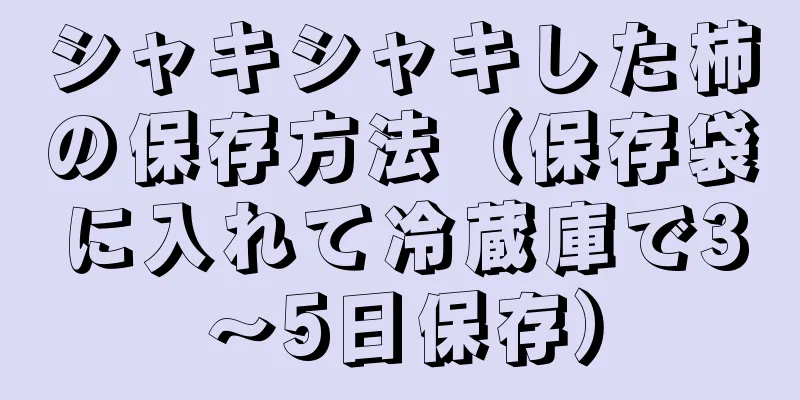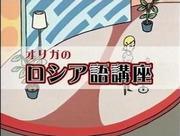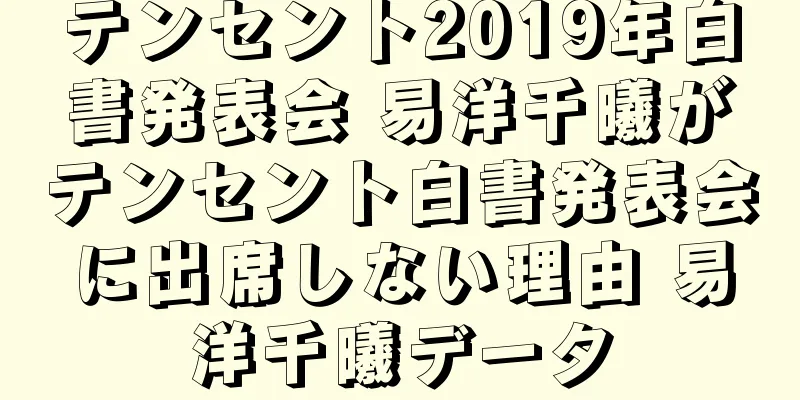肉を食べたいですか?腸内細菌叢と脳がこれを担当しています。
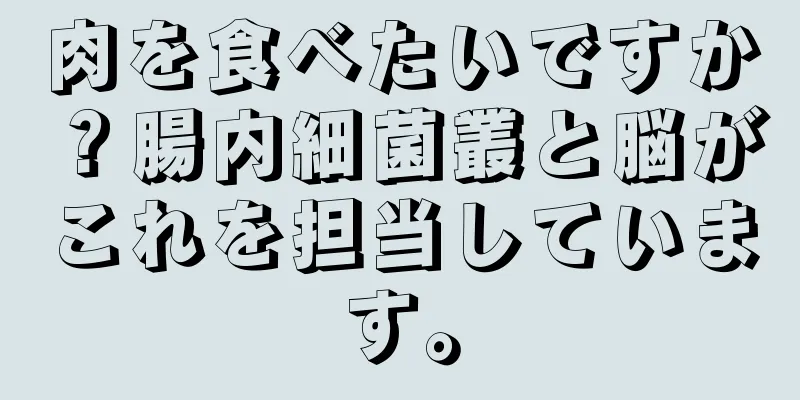
|
動物は健康を維持するために、炭水化物、タンパク質、脂肪などの栄養素をバランスよく摂取する必要があります。 肉はタンパク質が豊富ですが、タンパク質の他に動物性脂肪やコレステロールも多く含まれているため、摂りすぎると人体に害を及ぼします。 過剰なタンパク質には窒素が多く含まれており、脱アミノ化によって分解され、尿素に変換されて尿中に排泄されます。このプロセスには大量の水が必要となり、腎臓への負担が増加します。腎臓の状態が良くない場合、被害は大きくなります。 肉を食べすぎると硫黄含有アミノ酸を過剰に摂取することになり、骨のカルシウムの減少が促進され、骨粗しょう症につながります。 しかし、食事に十分なタンパク質が含まれていないと、深刻な栄養失調につながります。しかし、タンパク質の摂取が不十分な場合、動物はタンパク質や必須アミノ酸が豊富な食物を積極的に選択します。 韓国科学技術院とソウル国立大学の研究によると、ショウジョウバエの食物選択は腸と脳の「対話」によって左右され、タンパク質や必須アミノ酸を豊富に含む食物への欲求を調節しているという。 ショウジョウバエでは、腸内細菌-腸内脳系(一般に細菌-腸内脳系として知られる)が必須アミノ酸が不足しているかどうかを検出し、ショウジョウバエのこれらのアミノ酸に対する欲求を刺激することができます。 科学者たちは、生物が十分なタンパク質を摂取しないと、タンパク質や必須アミノ酸が豊富な食物を優先的に選ぶことを知っていますが、それがどのように起こるのかはよくわかっていません。 ミバエのタンパク質欠乏は、特定の腸細胞から神経ペプチド CNMamide (CNMa) と呼ばれる消化管ホルモンの放出を引き起こします。 CNMa は腸の栄養状態を脳に伝え、必須アミノ酸を含む食品を食べたいという欲求を引き起こします。 また、腸内細菌(アセトバクター菌)が食事中のわずかなタンパク質不足を補うことができるアミノ酸を生成することも発見した。 この細菌だけを補給すると、CNMa の放出を変化させ、ショウジョウバエの「肉を食べたいという」欲求を軽減できるアミノ酸が生成されます。 しかし、ロイシンや他のアミノ酸を生成しない変異腸内細菌を持つノトバイオートハエは、CNMaの発現が高く、食欲も旺盛でした。 腸管上皮細胞は食事や腸内細菌からアミノ酸レベルを感知し、CNMa を介して脳にアミノ酸欠乏を伝えます。 したがって、人間の体にも同様のメカニズムが存在する可能性があり、つまり、自分の欲望は必ずしも自分でコントロールできるわけではなく、腸内微生物も関与している可能性があるのです。私のコースの欲望についてのセクションに、より詳細な説明があります。 参考文献: ボラム・キム他ショウジョウバエにおけるマイクロバイオーム-腸管-脳系のアミノ酸欠乏に対する反応。自然、2021、doi:10.1038/s41586-021-03522-2。 |
<<: ゆでたての卵を殻をむくと、なぜ嫌な臭いがするのでしょうか? (ゆで卵は硫化水素のような臭いがします)
>>: 父が脳梗塞で亡くなるのを見て、私が感じた無力感は一生忘れられないでしょう。
推薦する
牛肉炒めにはどんな料理がよく添えられますか?牛肉と豚肉の違いは何ですか?
牛肉と豚肉は私たちのお気に入りの肉です。宴会では牛肉は通常、ジャガイモやピーマンと一緒に出されます。...
【医療Q&A】異なるブランドの狂犬病ワクチンは互換性がありますか?
企画者: 中国医師会評者: 黄磊、人民解放軍総合病院第五医療センター副主任医師狂犬病ワクチンは狂犬病...
国内では3億人以上が睡眠障害に苦しんでいます。どうすればぐっすり眠れるのでしょうか?
人間の人生の3分の1は睡眠に費やされます。質の高い睡眠は無形の財産であり、人々の睡眠に対する需要は高...
子どもたちがいつも教室の端に座って黒板を見ていると、目を細めるようになるのでしょうか?
斜視は子供によく見られる目の病気で、子供の視力や外見に悪影響を及ぼします。しかし、多くの親は斜視につ...
コンビネーションレンジフードの掃除のヒント(コンビネーションレンジフードを徹底的に掃除してキッチンを清潔に保ちましょう)
キッチンの空気を新鮮に保つために、コンビネーションレンジフードはキッチンに欠かせない器具の 1 つで...
ルーターの WiFi パスワードを変更するにはどうすればよいですか? (ホームネットワークを保護するための簡単な手順)
インターネットの普及に伴い、ホームネットワークのセキュリティはますます注目されるようになりました。ホ...
Midea ガスコンロを適切に掃除する方法 (ガスコンロを新品のように見せるためのシンプルで効果的な掃除方法)
正常な動作を維持し、耐用年数を延ばすには、Midea ガスストーブを定期的に清掃することが非常に重要...
不妊患者にとって無視できない感染症、マイコプラズマ・ジェニタリウム
2021年6月に発表された『ランセット 中国母子保健70年史』は、わが国では出産年齢の女性に占める不...
セルフ加熱ご飯のお米は実は「フェイクライス」!この米は何からできていますか?
自動加熱ご飯は怠け者にはありがたい存在です。調理に火をつける必要も、鍋や食器を洗う必要もなく、お好み...
なぜ「Maocai」は「Maocai Mao」と呼ばれ、どのような意味を持つのでしょうか?マオカイはどこから来たのですか?
マオカイは、肉、大豆製品、野菜、魚介類、キノコなどを主な材料として作られた料理です。成都発祥で、四川...
トランス脂肪酸:なぜ食品業界では「歓迎されない客」なのでしょうか?
食品のパッケージには「トランス脂肪酸ゼロ」や「トランス脂肪酸フリー」といった文字がよく見られます。こ...
タイトなスポーツブラを着用した方が良いのでしょうか?答えはあなたが思っているものと違います!
誤解:「スポーツブラを着用するときは、きついものの方がよい」 「運動するときはスポーツブラを着けなき...
三国志演義で曹丕はどうやって死んだのですか?三国志演義における曹植の性格的特徴は何ですか?
『三国志演義』には名前のある登場人物が1000人以上も登場します。数多く複雑な登場人物のうち、比較...
古代中国の文人の四つの芸術とは何ですか?古代中国の文人は紅包を何と呼んでいたでしょうか?
先人たちが追求の過程で得た教訓とその要約こそが、実は私たちがそこから学び、教訓を引き出すことができる...