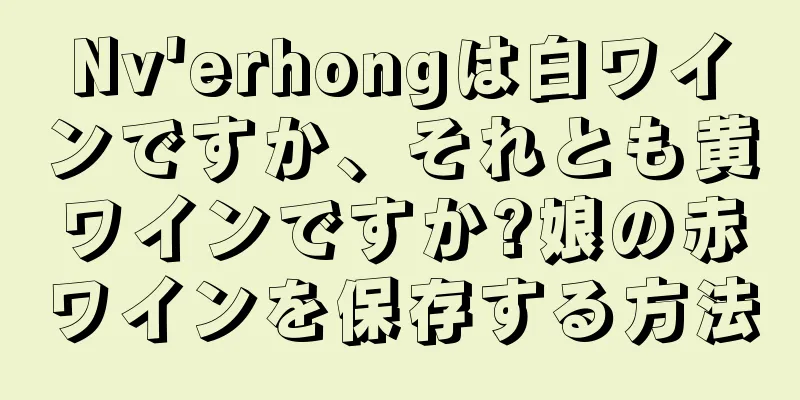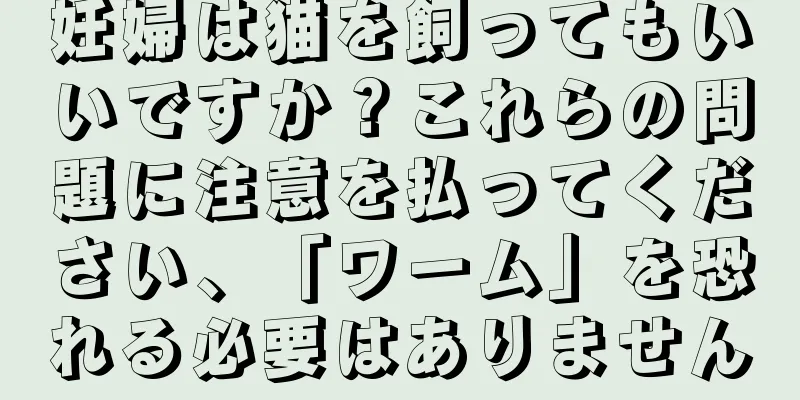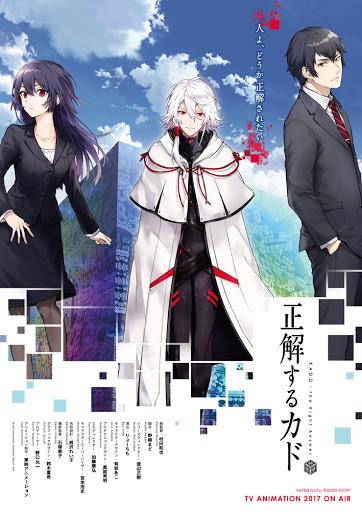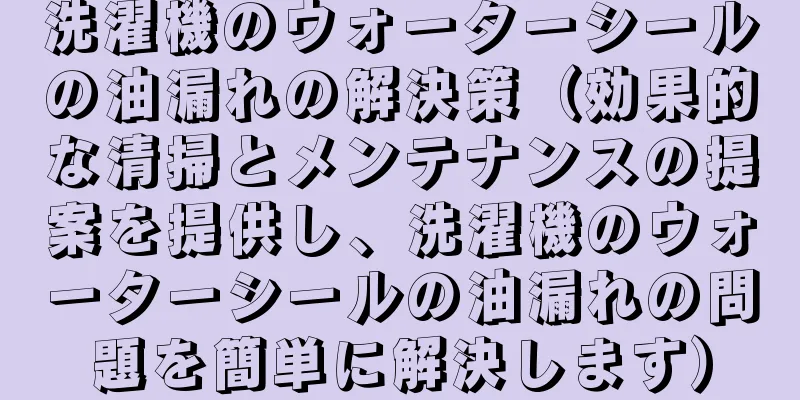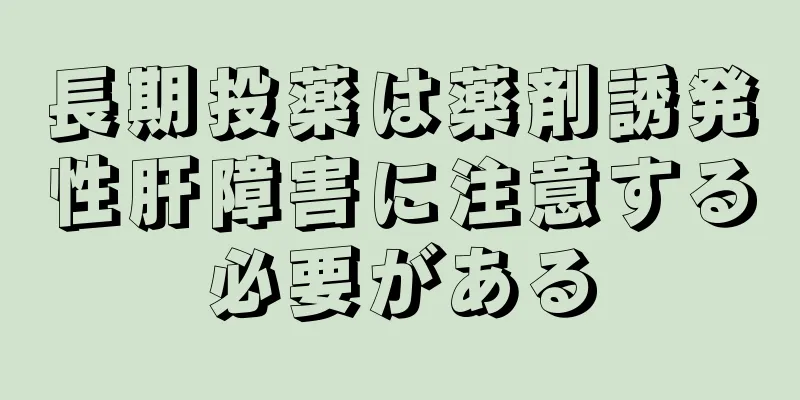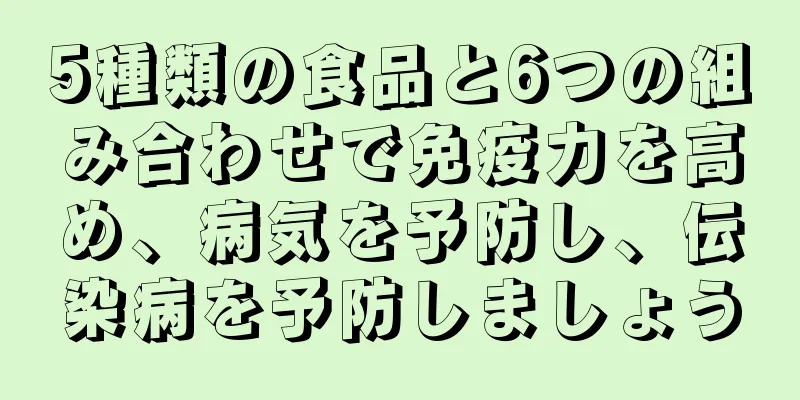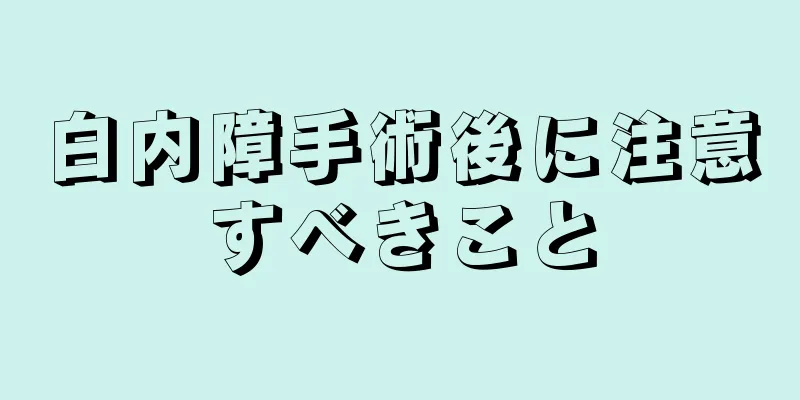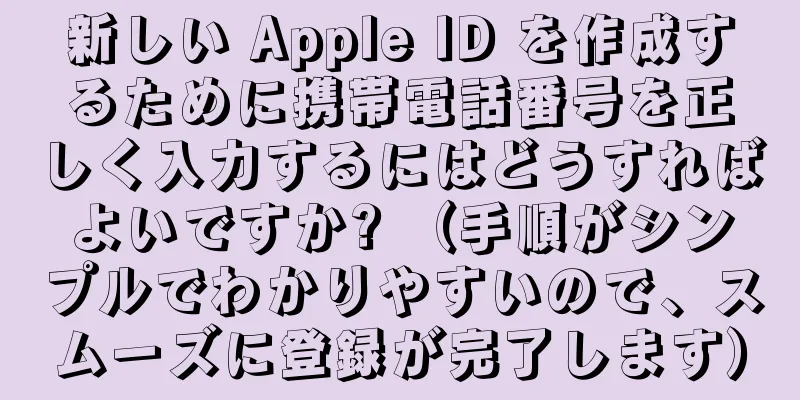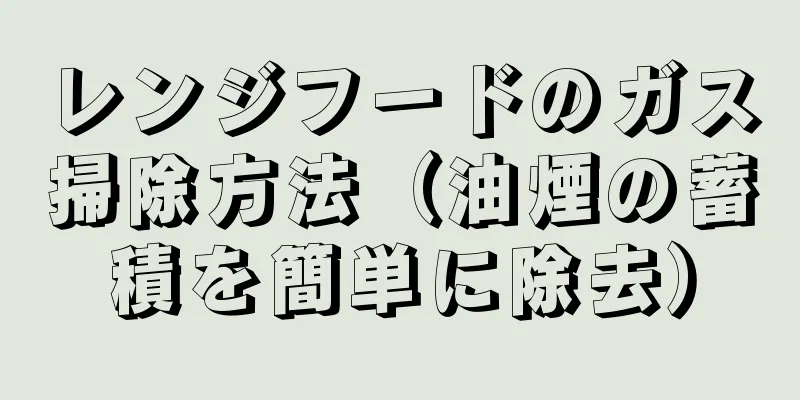中国の食事ガイドライン 2022 |原則3:果物、野菜、牛乳、全粒穀物、大豆をもっと食べる
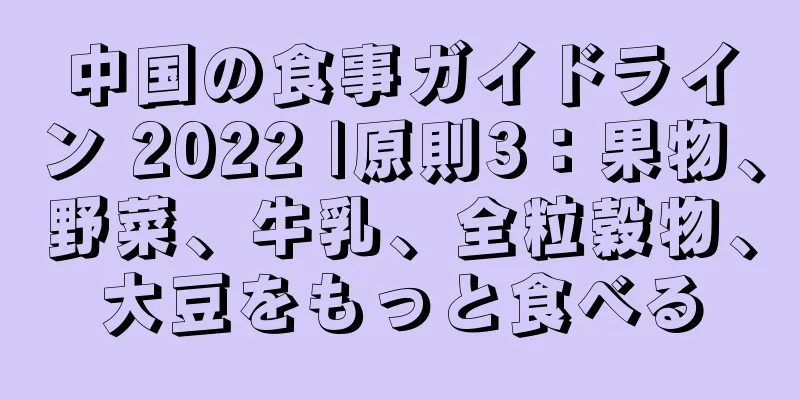
|
【コアレコメンデーション】 ● 果物、野菜、全粒穀物、乳製品はバランスの取れた食生活の重要な要素です。 ● 毎食に野菜を取り入れ、新鮮な野菜を1日300g以上摂取し、そのうちの半分を濃い色の野菜が占めるようにします。 ● 毎日果物を食べ、新鮮な果物を毎日200〜350g摂取するようにしてください。ジュースは新鮮な果物の代わりにはなりません。 ● さまざまな乳製品を摂取し、1日あたり液体ミルク300ml以上に相当する量を摂取してください。 ● 全粒穀物や大豆製品を定期的に摂取し、ナッツ類は適度に摂取してください。 野菜、果物、全粒穀物、牛乳、大豆は、ビタミン、ミネラル、高品質のタンパク質、食物繊維、植物化学物質の重要な供給源であり、食事の質を向上させる上で重要な役割を果たします。 【実用化】 1. 野菜や果物の選び方 1. 新鮮さを重視する 旬の新鮮な果物や野菜は、まるで生きている植物のように鮮やかな色をしています。水分量が多く、栄養分が豊富で、新鮮な味わいです。このような新鮮な果物や野菜を食べることは、人間の健康に多くの利点をもたらします。 2. 「色」を選択 野菜は色の濃さによって、濃い野菜と薄い野菜に分けられます。濃い野菜とは、濃い緑、赤、オレンジ、紫の野菜を指します。栄養的にも優れており、特にベータカロチンが豊富です。これらは食事中のビタミン A の主な供給源なので、より多く摂取するように注意する必要があります。 3. より「品質」を高める 野菜を選んで購入するときは、1日あたり少なくとも3〜5種類を選んでください(表1)。夏と秋は果物が最も豊富になる季節です。果物によって甘さや栄養成分が異なります。 1日に少なくとも1~2種類食べ、季節のフルーツが望ましいです。 表1: 一般的な野菜の種類 2.適切な果物と野菜の摂取目標を達成するには 1. 毎食野菜を食べる 食事では、まず野菜が重量の約半分を占めるようにして、1日の「量」の目標を満たすようにします。 2. 毎日果物を食べる 新鮮で旬の果物を選び、いろいろな種類を購入し、いつでも食べられるように、家や職場の目に付きやすく手の届きやすい場所に置いておきましょう。 3. 果物と野菜の賢い組み合わせ: 野菜料理に重点を置き、新しいレシピや組み合わせを試して、色とりどりの果物と野菜でテーブルを飾り、気分を明るくしましょう。 3. 野菜の栄養を保つための上手な調理 1.切る前に洗う 2.スープを添える 3.さっと炒める 4.揚げたらすぐに食べる 4.牛乳と大豆をもっと食べる方法 1. さまざまな乳製品を選ぶ ヨーグルト、チーズ、粉ミルクは液体ミルクと比べて風味やタンパク質濃度が異なるため、いろいろ試して食生活を豊かにすることができます。 2. 大豆とその製品は、さまざまな方法で頻繁に食べられる 豆腐、乾燥豆腐、千切り豆腐などの製品は、味を変えたり栄養ニーズを満たすために毎週ローテーションすることができます(図1)。 図1: 豆類の代替食品(タンパク質含有量別) 3. 乳製品と大豆製品を食生活の必須成分として考える 実際には、1日あたり300mlの液体ミルクに相当する量を達成することは難しくありません(図2)。 図2: 1日あたり300mlの液体ミルクに相当する乳製品(カルシウム含有量に基づく) カルシウム含有量データの出典:「中国食品成分表標準版(第6版、第2巻)」、2019年。 5. 食事の重要な要素としての全粒穀物と豆類 1. 全粒穀物は食事の良いパートナー 毎日50〜150グラムの全粒穀物食品を食べることが推奨されています。これは、1日の穀物摂取量の1/4〜1/3に相当します。 2. 小豆、緑豆、ピント豆を賢く使う ミックスビーンズは主食と一緒に食べることで、食物繊維、ビタミンB、カリウム、マグネシウムなどの栄養素をバランスよく摂取し、タンパク質の補完性と利用性を高める役割を果たします。 3. 現代の調理器具を有効活用する 全粒穀物は食べるとざらざらした感じがしますし、豆類は調理が難しいです。精製された米や小麦粉の柔らかい味に慣れている消費者は、全粒穀物や豆類を使用する際には、早い段階で適切な調理方法を学ぶ必要があります。 6. ナッツは良いが、食べ過ぎはよくない 適度な摂取は健康に良いので、そのエネルギーは1日3食の総エネルギーに含めるべきです。 7. 幼い頃から様々な食べ物を食べる習慣を身につける 親は、子どもが幼い頃から健康的な食習慣を身につけることに注意を払い、日常生活の中で健康的な食生活の雰囲気を作り、子どもの野菜、果物、牛乳、豆類などの食品に対する好みを高める必要があります。親もまた、子どもが親から学び、多様な食品を含むバランスの取れた食生活に適応できるように、自ら模範を示すべきです。 【主な事実】 ● 果物や野菜には、微量栄養素、食物繊維、植物化学物質が豊富に含まれています。 ● 野菜、果物、全粒穀物の摂取量を増やすと、心血管疾患や死亡のリスクを減らすことができます。全粒穀物の摂取量を増やすと体重増加が抑えられる可能性があります。 ●野菜の総摂取量を増やし、アブラナ科の野菜や緑葉野菜の摂取を増やすと、肺がんのリスクを減らすことができます。 ● 野菜、果物、全粒穀物を多く食べると、大腸がんのリスクを減らすことができます。 ● 牛乳とその製品は、子供や青少年の骨密度を高めることができます。ヨーグルトは便秘や乳糖不耐症を改善することができます。 ● 大豆とその製品には健康に有益なさまざまな物質が含まれており、閉経後女性の骨粗しょう症や乳がんのリスクを軽減するのに役立ちます。 1. 中国住民の野菜、果物、全粒穀物、牛乳、豆類、ナッツ類の摂取状況と動向 2015年の中国成人慢性疾患および栄養モニタリングデータによると、標準人1人あたりの野菜、果物、全粒穀物、牛乳、大豆、ナッツ類の1日あたりの平均摂取量はそれぞれ265.9g、38.1g、16.3g、25.9g、13.9gで、いずれも現在の中国の食事ガイドラインで推奨されている摂取量を下回っています(図3)。 図3: 中国住民の野菜、果物、全粒穀物、牛乳、大豆、ナッツの1日あたりの摂取量 2. 野菜、果物、全粒穀物、牛乳、豆類、ナッツ類の栄養特性と食事への貢献 野菜、果物、全粒穀物、牛乳、豆は人間の食生活の重要な要素です。人体に必要なビタミン、ミネラル、食物繊維、植物化学物質が豊富に含まれています。牛乳や大豆も高品質のタンパク質の重要な供給源です。 さまざまな年齢層の人々の食生活において、果物や野菜、全粒穀物、乳製品、豆類はすべて、人体に必要な微量栄養素や食物繊維を満たす上で重要な役割を果たします。 図4: 2000kcalのバランスの取れた食事における各種食品の栄養素への寄与 中国住民の野菜摂取量は減少している一方、果物、全粒穀物、牛乳、豆類の摂取量は大きな変化はないものの依然として比較的低い水準にあり、果物、野菜、全粒穀物、牛乳、大豆製品が食事栄養素に占める割合も低いという現状を考慮すると、これがわが国の18歳以上の成人のレチノール、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンC、カルシウムの摂取量が全体的に低い主な理由であると考えられます。したがって、β-カロチン、ビタミンB、ビタミンC、カルシウムの摂取量を増やすために、果物や野菜、全粒穀物、牛乳、大豆製品をもっと食べることが推奨されます。これは、中国住民の全体的な食事中の微量栄養素摂取不足を改善し、栄養失調の発生を減らすための効果的な措置であり、重要な保証です。 3. 野菜、果物、牛乳、豆と健康 表2: 野菜、果物、牛乳とその製品、大豆とその製品、ナッツと健康の関係 著者: ヤン・ユエシン食事ガイドライン改訂専門委員会委員長、中国疾病予防管理センター栄養健康研究所教授 ティアン・スー食事ガイドライン改訂専門委員会事務局長、河北医学大学准教授 |
>>: 「食から健康」シリーズ特別企画丨「口から病気になる」に注意、こんな食品を食べるときは気をつけて
推薦する
『仏典物語3 大きな願い -仏説無量寿径-』の魅力と評価
仏典物語3 大きな願い -仏説無量寿径- の詳細な評測と推薦 作品概要 『仏典物語3 大きな願い -...
ASUS ドライバーのダウンロードとインストール ガイド (ASUS デバイスの最新ドライバーをすばやく入手するための詳細なチュートリアルと注意事項)
デバイスのパフォーマンスを保証するために、ASUS はタイムリーに更新されたドライバーも提供していま...
コイとオオゴイの見分け方は?コイとオオゴイの違いは何ですか?
魚には多くの種類があることは誰もが知っていますが、ハクレンやコイは最も一般的な2種類です。食べ方もい...
足首を何度も捻挫する人は、慢性的な足首の不安定性に注意してください!
足首の関節は人体の中で重要な関節の一つです。日常の運動では、主に足首関節の背屈や底屈などの動作を行っ...
『おしえて!ギャル子ちゃん』の魅力と評価:ギャル文化の深層に迫る
『おしえて!ギャル子ちゃん』 - ギャル文化と青春の交錯 『おしえて!ギャル子ちゃん』は、2016年...
『A.I.C.O. -Incarnation-』の魅力と評価:サイバネティックな世界の深淵へ
A.I.C.O. -Incarnation- の全方位的評価と推薦 概要 『A.I.C.O. -In...
コナ ブルー フェイシャル クリーム ウォーターはどのような肌タイプに適していますか?コナブルーフェイシャルクリームウォーターの効果は何ですか?
コナブルークリームウォーターは、水とクリームを組み合わせたスプレーです。保湿効果が高く、肌の悩みを改...
親知らずを抜く必要はありますか?必ずしもそうではありません! |エキスポデイリー
親知らずを抜く必要はありますか?必ずしもそうではありません!親知らずは、成人後期に生えてくることが多...
『陰陽大戦記』の魅力と評価:見逃せない戦いの物語
陰陽大戦記 - オンミョウダイセンキ - の魅力と評価 2004年から2005年にかけて放送されたT...
囲碁のランクはどのように分けられるのでしょうか?囲碁はどんな能力を養うのでしょうか?
囲碁を学ぶ過程で、囲碁は包囲と破壊のゲームであり、常に考え、攻撃し、防御する必要があることに気づきま...
水冷式エアコンが冷えない原因と解決法(水冷式エアコンが冷えなくなる原因と解決法を探る)
しかし、時には冷却が効かないという問題が発生することがあります。皆様に水冷エアコンをより良くご利用い...
メロンの切り目の魅力と評価:みんなのうたの名作を深掘り
『メロンの切り目』 - みんなのうたの名作を振り返る 1993年8月にNHK教育テレビ(現在のNHK...
ACCA13区監察課:組織の秘密とキャラクターの魅力を徹底解剖
『ACCA13区監察課』 - 深遠なる組織の謎と人間ドラマの融合 『ACCA13区監察課』は、201...
中国居住者向け食事ガイドライン 2022 |高齢者のための食事ガイドライン
高齢者とは通常、80歳以上の人を指します。高齢や虚弱な高齢者は、食事摂取量が制限され、味覚、嗅覚、消...