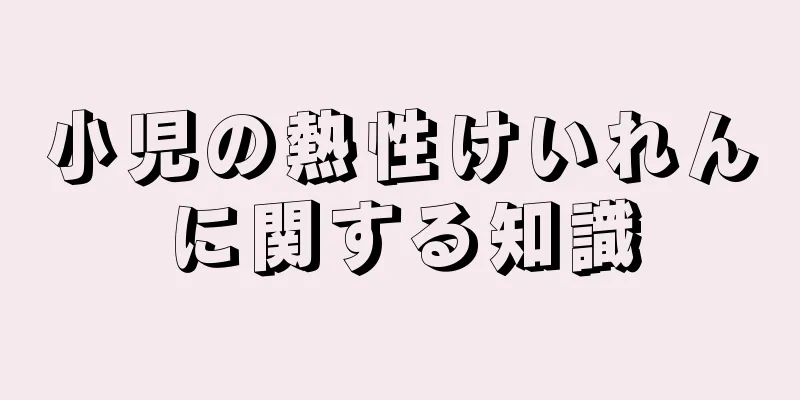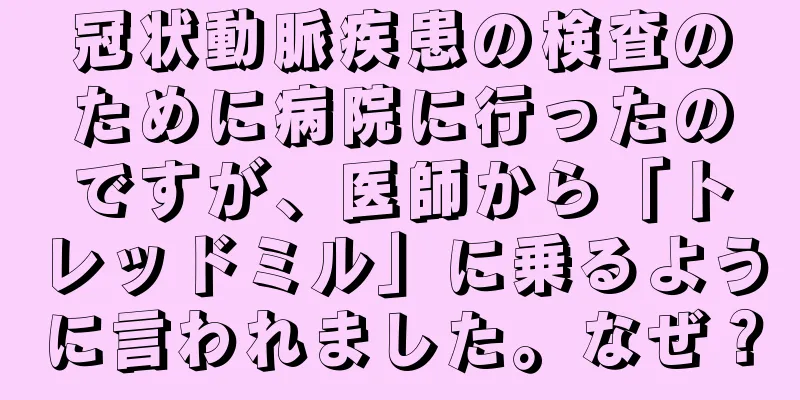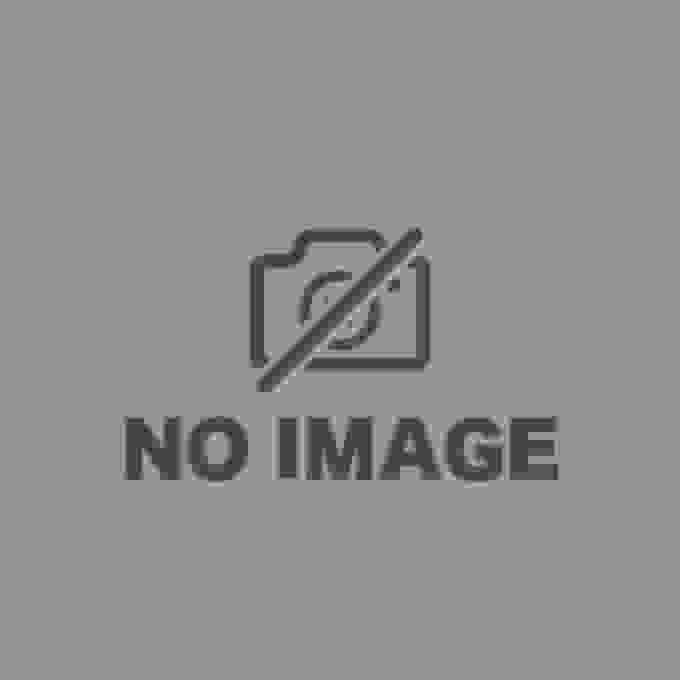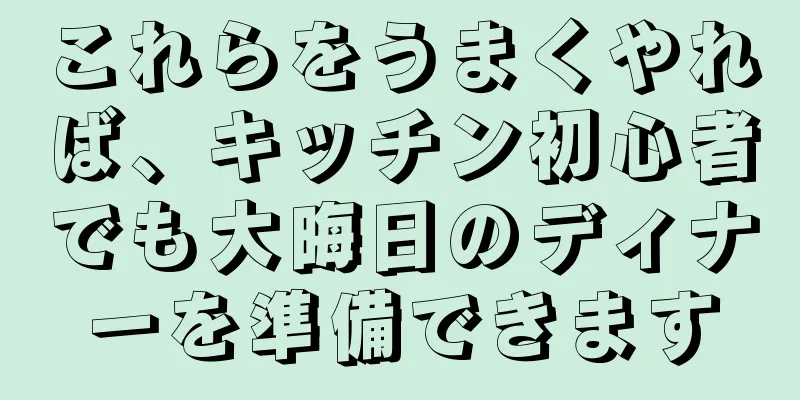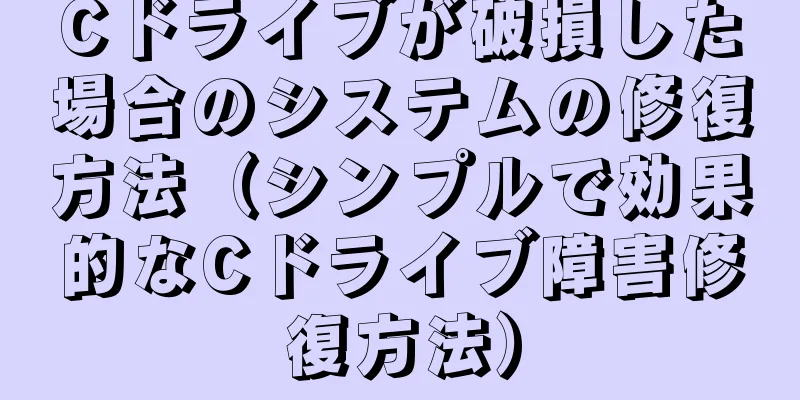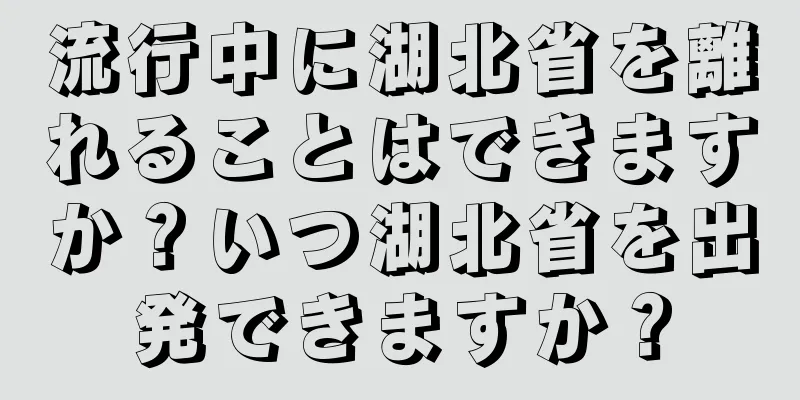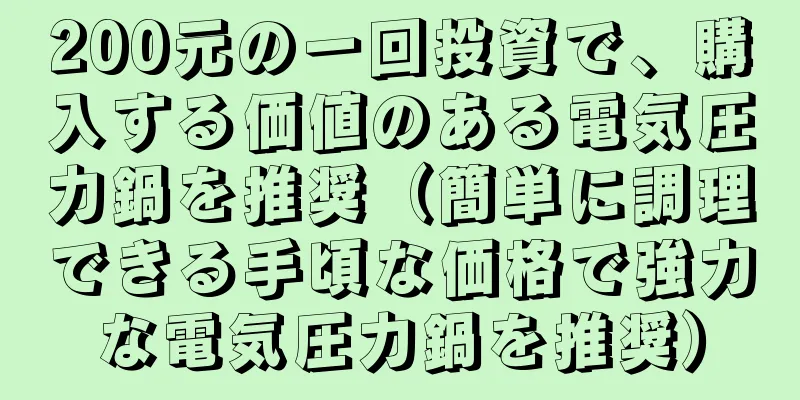『死者の書』レビュー:謎と恐怖の世界へ誘う傑作アニメ

『死者の書』:奈良時代の魂の物語■公開メディア劇場 ■原作メディア小説 ■公開日2006年02月11日 ~ 0000年01月01日 ■配給会社岩波ホール、株式会社 桜映画社 ■分数70分 ■話数1話 ■原作折口信夫「死者の書」より ■監督川本喜八郎 ■制作・企画/川本喜八郎新作人形アニメーション製作実行委員会 ■著作©2005株式会社桜映画社/有限会社川本プロダクション ■ストーリー時は奈良。大和の文化と大陸から渡来した華やかな文化がせめぎ合い溶け合った時代。平城京では大伴家持や恵美押勝らが、やまとごころや漢土(もろこし)の才(ざえ)について論じ合っている。大貴族である藤原南家の郎女は、当時の最も新しい文化――仏教に目覚め、称讃浄土経の千部写経を始めていた。彼岸中日の夕暮れ、郎女は荘厳な俤人(おもかげびと)が二上山の上にきらめき浮かび上がるのを見た。千部目の写経を果たした夕は雨、郎女はものに憑かれたように屋敷を出て、二上山のふもとまで来てしまう。そこは、女人禁制の当麻寺の境内である。 ■解説『死者の書』の時代設定は、奈良時代。平城の都の文化の爛熟する一方で、疫病や疫災が流行し、 天皇の病気平癒を祈願して東大寺の大仏が建立され、開眼供養の行われた時代。 富と権力を取り巻く権力者達の争いが繰り返されていた。万物に霊が宿ると信じられていた時、 大陸からもたらされた仏教が、ようやく社会に浸透しはじめた時代である。 ■キャスト・藤原南家の郎女/宮沢りえ ■メインスタッフ・原作/釈迢空(折口信夫) ■メインキャラクタ・藤原南家の郎女(ふじわらなんけのいらつめ) ■関連作品・序章 ひさかたの天二上 ■評論『死者の書』は、奈良時代の魂の物語として非常に興味深い作品である。監督の川本喜八郎は、人形アニメーションという手法を用いて、奈良時代の風景や人々の心の動きをリアルに表現している。これは、非常に挑戦的な試みであり、彼の技術と芸術性が高く評価されるべきである。 |
<<: チャーミーキティ Vol.2の魅力と評価 - チャーミー&フレンズの世界を深掘り
>>: 『火の鳥 アースキーパーズ篇』の魅力と評価:感動の物語と深遠なテーマを徹底解剖
推薦する
夏になるとすぐに背中にできる「小さなぶつぶつ」、これは何でしょうか?
警告!警告!警告! ...... ...... 出典: ドクターキュリアスこの記事は承認されました。...
流行中に妊婦が産前検診を受ける際に注意すべきことは何ですか?妊婦は出産前検診で新型コロナウイルスの感染をどう防ぐことができるのか?
新型コロナウイルスが最近全国各地で発生し、特に中高年層、もちろん一部の子どもや妊婦を中心に、多くの人...
美的レンジフード自動掃除の利便性と効果(キッチン掃除を安心にするインテリジェント掃除技術)
忙しい生活の中で、キッチンの掃除は常に頭の痛い問題でした。便利で快適なユーザー体験をもたらします。M...
携帯電話のフレームドロップ問題の解決(携帯電話のパフォーマンスを最適化し、フレームドロップ現象を解消)
日常生活で携帯電話を使用すると、フレームドロップ、つまり携帯電話の動作が遅くなったり、画面がフリーズ...
新しいモニターにシリアルポートがない問題を解決する(新しいモニターを接続するのに役立つシンプルで実用的な方法)
現代の技術の急速な発展により、新しいディスプレイは私たちの日常生活や仕事に欠かせないものになりました...
『怪獣がやってくる』:子供から大人まで楽しめる、みんなのうたの魅力とは?
怪獣がやってくる - カイジュウガヤッテクル 「怪獣がやってくる」は、1967年10月にNHK教育テ...
緑のキンカンを食べてはいけない人は誰ですか?緑のキンカンの食べ方
キンカンは、生で食べるほかに、ジュースやジャム、缶詰フルーツ、ドライフルーツ、ジャム、さらにはワイン...
トウモロコシの倒伏を防ぐにはどうすればいいですか?
トウモロコシは私たちの農家が栽培する主要な作物の一つです。トウモロコシの生産過程では、倒伏が頻繁に発...
【医療Q&A】子どもが咳喘息と診断された場合、親は何をすべきでしょうか?
著者:江西省小児病院副主任医師、何美娟評者: 江西省小児病院主任医師、李蘭お子さんが咳喘息と診断され...
4,000元前後のコストパフォーマンスの高いおすすめノートパソコン(4,000元前後を基準)
情報爆発の時代である今日、ノートパソコンは人々の生活や仕事に欠かせないツールとなっています。予算が限...
2,000元前後のおすすめコスパの良い携帯電話(2,000元で買う価値のある携帯電話)
しかし、あなたの言う通りです。この問題は消費者の根本的な要求ではありません。携帯電話を無料で購入する...
27歳の女性が転倒して骨折した。医者は彼女が骨粗しょう症だと言った。高齢者に多いこの病気がなぜ若者にも起こるのでしょうか?
27歳の王さんは、雨の日に滑りやすい道路で誤って転倒し、右上腕に痛みと運動障害を発症しました。 X...
『ブライト:サムライソウル』の魅力と評価:アニメファン必見の作品
『ブライト:サムライソウル』レビューと詳細情報 概要 『ブライト:サムライソウル』は、2021年10...
深8度希少疾患5 |杭州市が初めて希少疾患トップ10を発表、その名前を聞いたことがない人もいるかもしれない
第10回中国希少疾患サミットフォーラムが9月10日から12日まで杭州で開催され、会議で「浙江省希少疾...
『音響生命体 ノイズマン』の魅力と評価:音と物語の融合
『音響生命体 ノイズマン』:ビジュアルとサウンドの革新が織りなす15分間の奇跡 1997年11月22...