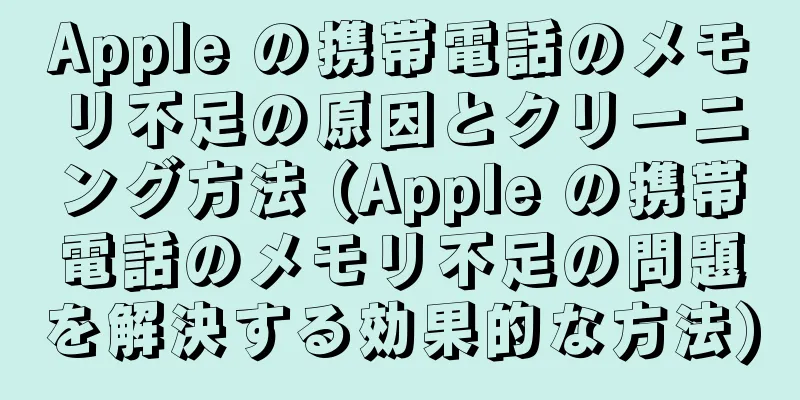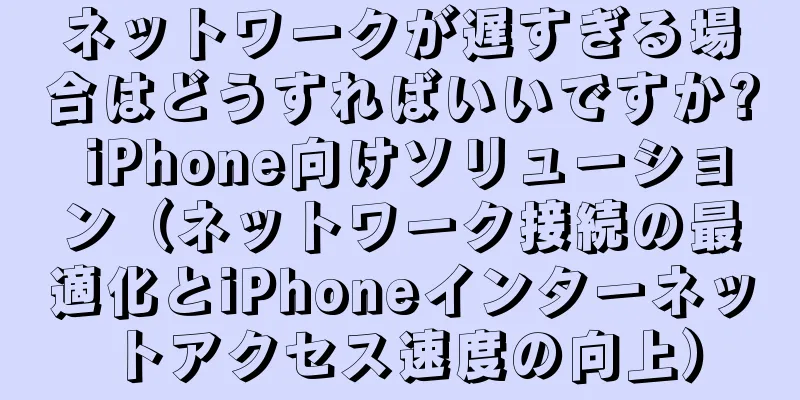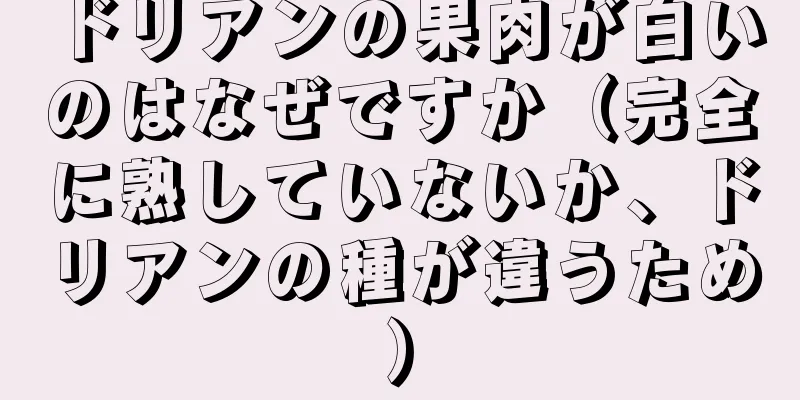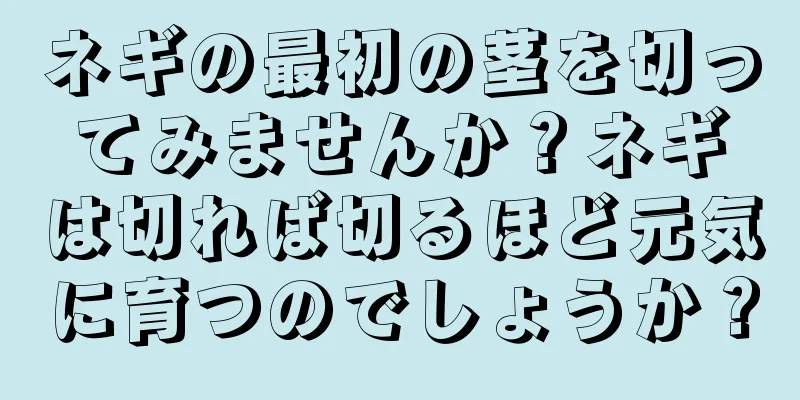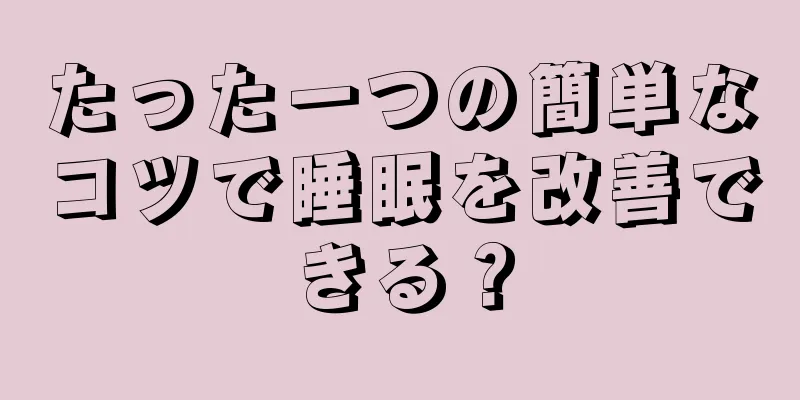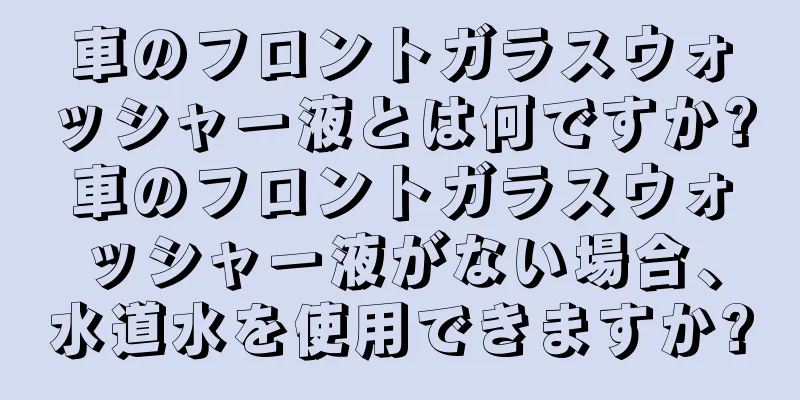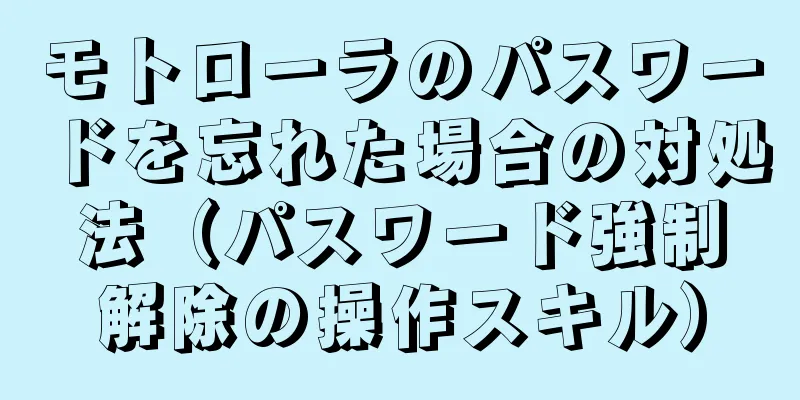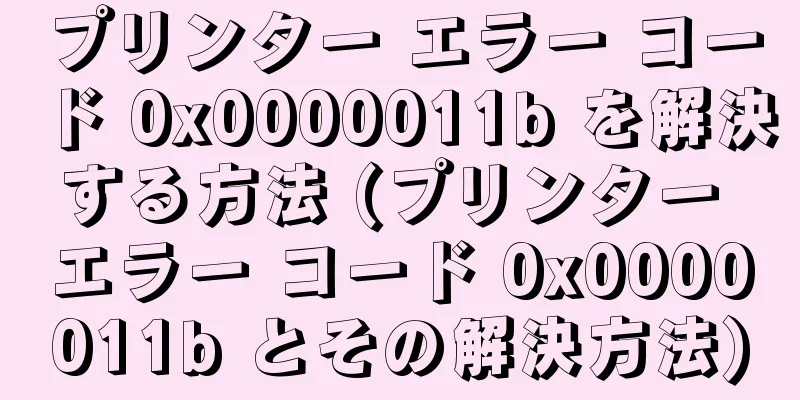何?あなたの声も老化しますか?
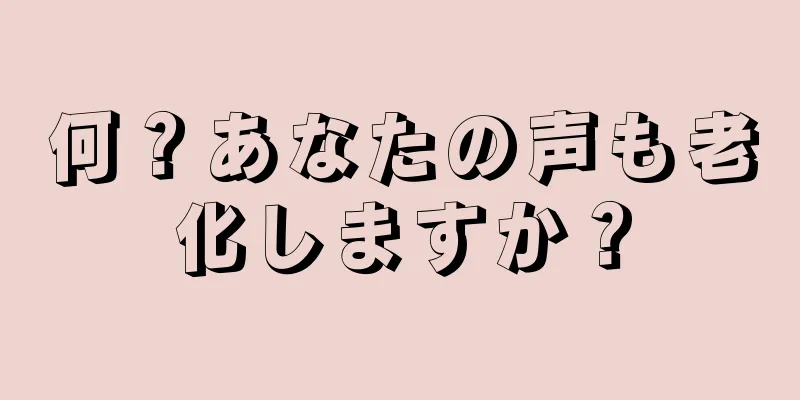
|
私たちは常に注意を払っています 年齢とともに外見は変化する でも、知ってる? 年齢とともに声は変化します。 人生において、私たちの声も異なります。オーディオパフォーマンスには、「女の子の声」、「女王様の声」、「若旦那の声」、「上司の声」などの特別なカテゴリもあります... では、こうしたさまざまな声はどのようにして生まれ、私たちの人生を通じてどのような変化を経るのでしょうか? 今日は以下のことを学習します。 声はどうやって出るんですか? 年齢によって発音が異なるのはなぜでしょうか? 喉を守るにはどうすればいいでしょうか? 声 声は人の「声の名刺」であり、人間がコミュニケーションをとり、情報を伝達する主な手段の 1 つです。 「人は皆、自分独自の声を持っている」と言うとき、体の中では5つの組織と器官に関わるプロセスが起こっており、決して単純なプロセスではありません。 声が話し言葉の意味を伝えることができるのは、動力器官、振動器官、共鳴器官、調音器官が神経系と連携して働くからです。脳は、脳幹反射、肺機能、胸壁のコンプライアンス、内喉頭筋の動き、咽頭、鼻、口腔の調節を調整します。 高次中枢の調節のもと、各臓器はそれぞれの機能を果たし、互いに協力し合います。パワーオルガンは呼吸器系(肺、気管、呼吸筋、胸郭など)の協力によって実現されます。私たちが吐き出す空気の流れは声門下圧を形成し、声帯を振動させます。 周知のように、声は声帯の振動によって生み出され、振動器官の関与が不可欠です。声帯は複雑かつ繊細な層構造を持つ組織です。関連する病気により、声がかすれたり、声が出なくなったりすることもあります。 発音器官の図 出典:北京デジタル科学センター 共鳴器官の追加により、世界中のあらゆる人の声が異なります。喉から発せられる音は共鳴腔(胸腔、咽頭腔、口、鼻腔、副鼻腔)内の空気を振動させます。 さらに驚くべきことは、共鳴室の長さ、形状、張力を調整することで、人々の表現ニーズに合わせてさまざまな効果を生み出す音が出ることです。一連の倍音と多音が形成され、ピッチ、強度、音色が生成されます。 独特な声を生み出す要因は、声帯と共鳴システムの自然な構造の違いという 3 つの大きな違いであると言えます。異なる筋肉調節能力;共鳴システムを使用するためのさまざまなテクニック。 言語は思考の武器であり、人々がコミュニケーションをとるためのツールです。しかし、中国語が普及する前は、「10マイルごとにアクセントが違う」というのは極めて一般的な現象でした。このような違いは、発音器官によって引き起こされました。 調音器官には、唇、舌、歯、口蓋、下顎が含まれます。口腔の形状や大きさを変えたり、声道内の空気の流れに影響を与えたり、母音や子音などの異なる音素を生成したりするなど、調音器官の相対的な位置を調整することで、異なる音声解釈を実現できます。私たちは単語を発音するときに、これらの違いを注意深く体験することができます。たとえば、平舌子音と反舌子音を発音するときには、舌の位置の変化が非常に顕著に表れます。 年齢によって声は違うのでしょうか? 年齢を重ねるにつれて、声も変わります。胎児は基本的に、生後3か月で喉頭の解剖学的構造のほとんどの成長を完了します。喉頭の発達は生後 3 年間に顕著になり、6 歳以降は変化が少なくなります。 この段階は「子供の声の段階」と呼ばれ、大人よりも明るい音色と高いピッチを持ちますが、大人よりも低い音域と豊かな音色が特徴です。現時点では、人間の声帯と発声器官全体はまだ完全には発達していません。 幼少期には、喉頭の発達や声帯の長さ(約6~8mm)と厚さが似ているため、男性と女性の声が似て聞こえます。 思春期を迎えると、子供の声から大人の声へと声変わりの時期が始まります。この段階では、発声器官と体のすべての器官が急速に発達します。思春期には声が大きく変化し、徐々に性差も現れてきます。男の子の声はだんだんと低くなり、女の子の声は高くて細くなっていきます。 具体的には、この段階では、女児の喉頭は狭くなり、声帯は短く細くなり、長さは15~20 mmになり、振動周波数が高くなります。男児の喉頭腔は大きくなり、声帯は幅広で厚くなり、長さは20~25 mmになります。 一般的に言えば、女の子の声が変わる年齢は10歳から18歳の間ですが、 8歳から15歳で始まり、12歳から16.5歳で終わることもあります。男の子の声が変わる平均年齢は11歳から15歳です。声変わり期を過ぎると、人の声は固定されず、声も老化していきます。 人は年をとるにつれて、声が小さくなり、かすれてきます。これは喉の軟部組織が弱くなり、声の音色、大きさ、質に影響を与えるためです。 人の声は65歳を過ぎると衰え始めます。この時、女性の声はどんどんかすれ、音質もどんどん低くなり、一方、男性の声は弱々しくなり、音質もどんどん高くなっていきました。 喉を守るためのヒント 皆さん、喉を守りたいなら、次のことをお勧めします。 1. 喉を温める 授業や歌、その他の作業に参加する前に、肩と首のストレッチ運動を行ってください。さまざまなビブラートを作り、唇と舌を動かします。 2. 禁煙が推奨される タバコに含まれるタールと燃焼時に発生する有害ガスは、どちらも喉に強い刺激を与えます。 3. 音量を調節する 常に叫ぶのではなく、控えめに応援したり叫んだりしてください。 4. 温かい水をもっと飲む 喉が痛いときは、喉を潤すために温かい水を多めに飲んでください。 5. 胃酸の逆流に注意 喉に有害です。頻繁に胸焼けが起きたり、朝に口臭がしたり、しゃっくりが頻繁に起こったり、喉に何かが常に詰まっている感じがしたり、声がかすれたりする場合は、すぐに医師の診察を受ける必要があります。 6. 口腔衛生に注意する 口呼吸の習慣を直すために、毎朝、毎晩、食後に歯を磨きましょう。寒いときや風の強いときに外出するときはマスクを着用してください。 |
<<: 持続的腎代替療法中のダウンタイムを正確に判断するにはどうすればよいでしょうか?
>>: 結膜炎が急速に広がっていますが、どのように対処すればよいでしょうか?
推薦する
ニキビのワクチンが誕生する!ニキビを防ぐためにはどのように食べればよいでしょうか? 5つの提案が整理されています
最近、「#ニキビに効くワクチンができる」が話題になっています。ディスカッションエリアにいる全員を見る...
男性はなぜ胸を触るのが好きなのでしょうか?男性が女性にキスをするときに胸を揉むのが好きな理由
彼氏とハグするとき、近づきすぎて胸が彼氏の胸に触れてしまうのではないかといつも不安で、とても恥ずかし...
太陽熱温水器の水漏れ検査方法(太陽熱温水器の水漏れ問題を解決するための実践的なヒント)
しかし、使用中に水漏れの問題が発生する場合があります。太陽熱温水器は、現代の家庭で一般的な給湯装置の...
それはワックスアップルかミストロータスか知っていますか?ワックスアップルの名前は何ですか?
ワックスアップルは、フトモモ科のフトモモ属の熱帯果樹です。私の国におけるワックスアップルの主な生産地...
スキンケアに酸スクラブが必要なのはなぜですか?
酸ピーリングはスキンケア業界で流行していると言えます。多くの人がトレンドに従って酸ピーリングを行って...
アルスラーン戦記 Ⅳ『汗血公路』の魅力と評価:角川書店版第4巻の深掘り
『アルスラーン戦記 Ⅳ (汗血公路)』の詳細な評測と推薦 『アルスラーン戦記 Ⅳ (汗血公路)』は、...
『シドニアの騎士』レビュー:壮大な宇宙戦と深遠な人間ドラマの融合
シドニアの騎士:宇宙の果てで紡がれる人類の希望と戦い 「シドニアの騎士」は、弐瓶勉による同名の漫画を...
ガス壁掛けボイラー水ポンプのメンテナンス価格の詳細な説明(水ポンプのメンテナンス費用の重要な要素とメンテナンスサービスを選択するためのヒントを理解する)
水ポンプが故障する可能性があり、修理または交換が必要になります。ガス壁掛けボイラーの水ポンプは、お湯...
『聖闘士星矢 Legend of Sanctuary』レビュー:CGアニメの新たな挑戦とその評価
『聖闘士星矢 Legend of Sanctuary』 - 伝説の聖闘士たちの新たな挑戦 1986年...
黄雷のスプライトヌードルはいくらですか?どこで購入できますか?黄雷のスプライトヌードルは美味しいですか?味はいかがですか?
黄磊が『人生への憧れ』の中でさまざまなおいしい料理を作っていることは、誰もが知っています。スプライト...
風味を損なわずに塩分を減らす秘訣
中国住民の食生活における塩分摂取量は一般的に高く、塩分の過剰摂取は高血圧のリスクを高めます。調査によ...
Bluetooth ヘッドフォンのペアリングをリセットする方法 (ヘッドフォンを再度ペアリングするための簡単な手順)
しかし、Bluetooth ヘッドセットは現代生活に欠かせないデバイスの 1 つになっており、デバイ...
iPhoneで簡単にスクリーンショットを撮る方法を教えます(簡単な操作でスクリーンショットをもっと撮れます)
テクノロジーの進歩により、iPhone のスクリーンショットは私たちの日常生活に欠かせないものになり...
『ねずみくんのチョッキ』第1話の感想と評価
『ねずみくんのチョッキ ①』の魅力と評価 『ねずみくんのチョッキ ①』は、1997年7月21日に東映...